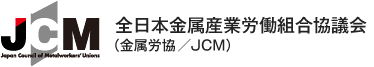�|�����ͣ�����߂āA�o�ρA���̂Â���̍Đ���
�ΘJ�Ґ����̈�����| |
�Q�O�O�S�N�Q���Q��
�S���{�����Y�ƘJ���g�����c��
�i�h�l�e�|�i�b�^�����J���j |
�@�����J���͍�N11�����A��46�c�ψ���ɂ����āA2004�N�����ɗՂދ����J���̕��j�Ƃ��āu2004�N�����̐��i�v������A����Ɋ�Â��āA�i�b�e�Y�ʂ͂��ꂼ����g�݂�i�߂���܂��B
���́u2004�N�����~�j�����v�́A����ȍ~�̌o�ϓ����A�Ȃ�тɌo�c���̔����Ȃǂ܂��A��A�E�P�g�ɂ�����c�̌��Ɍ�������b�����Ƃ��č쐬�������̂ł��B
�킪���o�ς́A�ɂ₩�Ȍi�C������ǂ��Ă��܂��B���������̂Ȃ��ŁA���ۋ����ɏ��������Ă������߂ɂ́A��Ƃœ����u�l�v���d�����A�ΘJ�҂̎����x�ȋZ�p�E�Z�\������Ɍp���E�琬���A���ꂪ�~�ς�������m�b�A�m�E�n�E�Ȃǂ����p���Ă������Ƃɂ���āA���̂Â���Y�Ƃ̍������Y��Ղ��ێ����A�������Ă����ȊO�ɂ͂Ȃ��Ƃ����F�����A�J���g���͂������A�o�c�҂݂̂Ȃ���A���{�A�}�X�R�~�Ȃǂɂ����܂��Ă��A�L����������Ă����Ƃ���ł���܂��B
�������Ȃ��炻�������Ȃ��ɂ����Ă��A���{�o�c�A�́u�o�c�J������ψ���v�́A�l����̈��������E�ϓ���ւ̎咣������ɋ��߁A�菸�p�~�A�x�[�X�_�E���Ȃǂ��咣���Ă��܂��B���������咣�́A�����l�̃��`�x�[�V�������ނ�������ƂƂ��ɁA������A���O���T�N�\���E���f���̌o�c�ւ̎w������������Ƃ���Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B
�����́A���������o�J�ϕ̎咣���A�킪���̎Y�ƌo�ς̐i�H����点����̂ł���A�܂��ΘJ�҂��琶���̈��S�E�����D���Ƃ����_�ŁA�����̗ǎ�����o�c�҂݂̂Ȃ���̋C�����Ƃ͈قȂ���̂ł��낤�ƍl���܂��B��������ٗp����{�Ɍ���̗͂��d������o�c�́A�m�̓������킸�G�N�Z�����g�E�J���p�j�[�ɋ��ʂ���l�����ł���܂��B�����́A�o�J�ϕ̌��͌��Ƃ��āA�F���̈Ⴂ�͈Ⴂ�Ƃ��āA���m�Ɏ咣���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
���̃~�j�����́A���ۂɒc�̌��̂��߂̎����Â���ɂ�������A��A�E�P�g�̏��L�����邢�͒��������A�����������Ƃ������݂Ȃ����O���ɂ����č쐬���Ă��܂��B��Z�p�I�ȕ������܂܂�Ă��܂����A����ǂ̂����A���ꂼ��̏ɉ����Ă����p���������܂��悤�A���肢�\���グ�܂��B
��N�̃~�j�����ɂ����āA2003�N�����͒�������ٗp�ɗ��Â���ꂽ���x�n���̋Z�p�E�Z�\�̒~�ςƔ����ɂ���č��ۋ����͂̊m�ۂ�}��̂��A���邢�͒�����E�ᐶ�Y�����Î�̂��A�܂��ɂ��̍��́u���̂Â���̂������v��₤���g�݂ƂȂ�A�Ǝ咣���܂����B���̒��̗���́A�܂��ɂ����̍l����O�҂̕����ɕω����Ă��Ă��܂��B�u����́v�����߂āA�킪���o�ς̍Đ��Ƃ��̂Â���Y�Ƃ̕������A�����Ă����ɓ��������ΘJ�҂̐�����Ղ̈�����߂����A�Ƃ��ɂ����܂��傤�B
�Q�O�O�S�N�Q���Q��
�S���{�����Y�ƘJ���g�����c��
�@�@�@�i�h�l�e�|�i�b�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ǒ� ���@��@�v�@�� |
�@�@�@�@�@�@�@
�P�D�ŋ߂̐l����̓����ƘJ�����z��
(1) �s�����ɂ�����l����ƘJ�����z���̒ቺ
�@�����̂Ȃ��A�s�����ɂ���������̉����d�����ƘJ�����z���̏㏸
�@���{�o�c�A��2003�N12���ɔ��\�����u2004�N�Ōo�c�J������ψ�����v�ł́A�t�����l���Y���Ɛl����̊W�A���Ȃ킿�J�����z���Ɋւ��āA
�������I�ɕ���������������f�t�����ł́A�i�����j�J���̑Ή��ł�������ɂ��āA�]���ȏ�ɕt�����l���Y���i�]�ƈ��P�l�����肪���ݏo�����t�����l�j�ɏ������Ă̑��z�l����Ǘ���O�ꂵ�Ă����K�v������B�iP.43�j
���l����̑��z���ς��Ȃ��Ƃ��Ă��A�t�����l����������A�J�����z���͏㏸����B�i�����j�t�����l���������Ȃ��Ȃ��ł̘J�����z���̏㏸�́A��Ƃ̗̑͂���߁A��Ƃ̑��������낤��������B�iP.43�j
���f�t�����ɂ����Ă�����I�ɏd�v�ƂȂ�̂́A���オ�����Ă��t�����l������Ȃ��o�c�ł���B�O���w���̌��ޗ��R�X�g�Ȃǂ̈���������Y�����㓙�X�̘J�g�̓w�͂ɂ���ĕt�����l���ێ��E����ł��Ȃ���A�l��������炳��������Ȃ��B�iP.44�j
���J�g�ɋ��߂���̂́A�J�����z���̓K�ȊǗ��A���Ȃ킿�t�����l���Y���̏㏸���͈͓̔��ɐl����̏㏸����}���邱�Ƃł���A���ꂪ�ł��Ȃ���ΘJ�����z���̏㏸��}���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�iP.44�j
���t�����l���Y���̏㏸�����}�C�i�X�ɂȂ�A�l��������炷�Ƃ����o��Œ���������s�Ȃ��p�����K�v�ł���B�iP.44�j
���f�t�����ɂ����ẮA���̏��i��T�[�r�X�ɔ�ׂĒ��������������ω����Ȃ��Ƃ��������̉����d��������茰���ɕ\���A����̌ٗp�ɗ^����e�������O�����B�iP.45�j
�ȂǂƎ咣���Ă��܂��B
�o�J�ϕ̂Ȃ��ł́A�Ȃ���̓I�ȃf�[�^���������A���͂����邱�ƂȂ��ɁA�Ђ�����u�����̉����d�����v�ɂ��u�J�����z���̏㏸�v�����O���Ă���̂������ł��B�}�\13�Ƃ��āu��v���̒P�ʘJ���R�X�g�i�S�Y�ƁA�����Ɓj�v�Ƃ����O���t���f�ڂ���Ă��܂��iP.45�j���A������A�u�����̉����d�����v��u�J�����z���̏㏸�v���������̂ł͂���܂���B
�@�܂����ӂ��ׂ��Ȃ̂́A�u�t�����l���Y���̏㏸�����}�C�i�X�ɂȂ�A�l��������炷�v�Ƃ����\���ł��B�������肷��ƁA�u�t�����l���Y���̏㏸�����݉�������v�Ƃ����Ӗ��ɍ��o���Ă��܂������ł����A����͖��炩�ɁA
�u�t�����l���Y���̏㏸�����}�C�i�X�ɂȂ�v
���u�t�����l���Y���̏㏸�����}�C�i�X�̕����ɂȂ�����v
���u�t�����l���Y�����ቺ������v
�Ƃ����Ӗ��ł��B�t�����l���Y�����㏸���Ă���̂ɁA�㏸�����݉����������ŁA�u�������v����Ă���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�\���Ȓ��ӂ��K�v�ł��B
�@���{�o�c�A������������ɂ�����A�ʊ�ƌo�c�Ҍ����̃}�j���A���Ƃ��č쐬���Ă���u2004�N�ŏt�G�J�g���̎�����v�ł́A�J�����z���̓����ɂ��āA�ꉞ�f�[�^�������Č��y���Ă��܂����A
�������Ƃɂ����鎑�{���P���~�ȏ�̑��Ƃ̐��ڂ��݂Ă݂�ƁA�ߋ�12�N�Ԃ̂����U�N�ԂłP�l�����葍�z�l����̐L�ї����t�����l���Y���̐L�ї��������Ă���B���Ȃ킿�J�����z�����㏸���Ă��邱�ƂɂȂ�B�iP.58�j
�Ǝw�E���Ă��邾���ł��B12�N�Ԃ̂����U�N�ԂŘJ�����z�����㏸���Ă����Ƃ��Ă��A�c��̂U�N�Ԃ͒ቺ���Ă���킯�ł��B�u������v�Ɍf�ڂ���Ă���O���t�Ō��Ă��A94�N�x�ȍ~�ɂ��Ă͂X�N�Ԃ̂����U�N�ԂŘJ�����z�����ቺ���Ă��܂��B�����J�����Z�o�����~�N���x�[�X�i��Ǝ��v�x�[�X�j�̘J�����z���i�����Ɓj�ł��A2002�N�x�͍ŋ߂T�N�Ԃ̂����łQ�ԖڂɒႢ�����ƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\�P�j
�@2003�N12���ɔ��\���ꂽ����u�Z�ρv�ł��A�����Ɓi�S���E�K�͌v�j�̐l����́A98�N�x����2003�N�x���ь����݂܂ŁA�U�N�A���őO�N��������Đ��ڂ��Ă��܂��B���̂��ߔ��㍂�l����䗦���A98�N�x�ɂ�15.08���ł������̂��A2003�N�x���ь����݂ł�13.55���ƁA�T�N�Ԃ�1.53�|�C���g���ቺ���Ă��܂��B����ŁA���㍂�c�Ɨ��v���͓����T�N�Ԃ�2.86������4.36����1.50�|�C���g�㏸���Ă���A���傤�ǐl����̍팸�����A���̂܂܉c�Ɨ��v�ɂȂ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�����������Y�Ƃł́A���̊Ԃ̔��㍂�l����䗦�̒ቺ����1.44�|�C���g�ƂȂ��Ă���A�����ƑS�̂Ƃ��܂�ς��܂��A���㍂�c�Ɨ��v����1.98�|�C���g�̏㏸�ƂȂ��Ă���A�l����̍팸�ȊO�ł����v���グ�Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�i�}�\�Q�j
�A���{�ł́A�����͂��Ƃ��Ə_��ŁA����ɕϓ�����i��ł���
�@�J�����z���́A�{���Ȃ�Γ��{�o�c�A���咣����Ƃ���A�����̉����d�����ɂ���ĕs�����ɂ͏㏸����͂��̂��̂ł��B�A�����J�ł́ATruman F. Bewley �i�G�[����w�����j�́gWHY WAGES DON`T FALL DURING A RECESSION�h �i�s���̊ԂɂȂ�������������Ȃ��̂��j�Ƃ������Ђ��钘�삪����܂��B�i1999�N�A�n�[�o�[�h��w�o�Łj
�@�������Ȃ�����{�ł͏]������A
����������̌��N�s���Ă���Ƃ��낪�����B
������O�����̔䗦�������B
���ꎞ���̔䗦�������B
���Ƃɂ��A�l����̉����d�������R�����A�_��Ȃ��̂ł����B�����čŋ߂ł́A
�������E�������x�̌������ɂ��A�l����̗}���E�������������{����Ă����B
�����Ј��ȊO�̌ٗp�̔䗦�����債�Ă���B
���Ƃɂ��A�l����̕ϓ���͂܂��܂��i��ł��܂��B���Ȃ��Ƃ���q����}�N���x�[�X�i�f�c�o�x�[�X�j�̘J�����z���Ō���A���{�ł́A�u�����̉����d�����v�A�u�s�����̘J�����z���̏㏸�v�͌��z�ɂ����܂���B
�A�����J�̂悤�ɁC�l��������d�����������Ă��āA�s�����ɘJ�����z�����㏸����Ƃ������Ƃ́A�s���ł��l�������قǗ������܂Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ����A�l����o�ς̃r���g�E�C���E�X�^�r���C�U�[�i�������艻���u�j�̖�ڂ��ʂ����āA�i�C�ꊄ���h�����ʂ�����܂��B
�c�O�Ȃ���킪���̐l����́A�s�����ɉ����d�����������Ă��炸�A�ϓ�����_��͂܂��܂��i��ł��܂��B�l����̕ϓ���́A�ʊ�Ƃ̌o�c�҂ɂƂ��ẮA�o�c���y�ɂ��邱�ƂɂȂ�܂����A���̂��́A���ׂċΘJ�Ґ����ƃ}�N���o�ςɂ������Ă���̂��Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) �}�N���x�[�X�i�f�c�o�x�[�X�j�ł̘J�����z��
�@���{�o�c�A�̓}�N���x�[�X�i�f�c�o�x�[�X�j�̘J�����z����������
�@��N�i2003�N�Łj�̌o�J�ϕł́A�u�ٗp�ҏ���(�}�})(�i�b���F�ٗp�ҕ�V�̂���)�����������v�Ƃ�����`�̘J�����z���̐��ڂ��O���t�Ŏ����iP.58�j�A�u��Ƃ̕t�����l�ɐ�߂�l����̊������J�����z�����㏸���āv����Ǝ咣���Ă��܂����B�iP.57�j
�@�����J���́A����ɑ���2003�N�Q���A���{�o�c�A�ɑ�����J���������\���A
�����{�o�c�A�������Ƃ��Ă���u�ٗp�ҕ�V�����������v�Ƃ����f�[�^�́A����Ɏ��c�Ǝ҂��Y�ݏo�����t�����l���܂�ł���̂ŁA��i���Ƃ��Ă͎��c�Ǝ҂̔䗦���傫���A�p�Ƃ��i�ށi���c�Ǝ҂��ٗp�҉�����j�ߒ��ɂ���킪���ł́A�㏸����X���������Ă���B�]���āA���̘J�����z�����㏸���Ă��邩��Ƃ����āA�u��ƌo�c���������Ă���v�Ƃ͂����Ȃ��B
���u�ٗp�ҕ�V�����������v�ł́A����Ɍ������p���܂܂�Ă��Ȃ��̂ł�����㏸�X���������ƂɂȂ�B�i���q�̌ٗp�ҕ�V�ɂ́A�ٗp�҂̌������p�i���q���̗{���j���܂܂�Ă���̂�����A����ɂ��������p���܂܂�Ă�����ׂ��Ƃ̎�|�j
�ȂǂƎw�E���܂����B
�@����ɑ��ē��{�o�c�A�́A2003�N�S���A�u�S���{�����Y�ƘJ���g�����c��̎����Ɋւ��錩���v�\���܂������A�����ł́A�u�g�p���Ă���f�[�^�̂Ƃ���́A�]�������т����l���̂��Ƃōs���Ă���v�Ƃ̌����������Ɏ~�܂�܂����B�܂��A�U���ɍs���������J���Ɠ��{�o�c�A�̎������x���̈ӌ������ł��A���{�o�c�A�̎g�p���Ă���J�����z���́A���t�{�ł��g�p���Ă���A�悭�g����f�[�^�ł���A�Ƃ̌��������������ł����B
�@���{�o�c�A���g�p���Ă���J�����z�����A�t�����l�̋ΘJ�҂ւ̔z���̓x�����������w�W�Ƃ��ēK�����ǂ��������ƂȂ��Ă���̂ɑ��A�u�]������g���Ă���v�u�悭�g���Ă���v�ł́A�ɂȂ�Ȃ��͖̂��炩�ł����B���������o�܂��o�āA����u2004�N�Ōo�J�ϕv�A�����āu2004�N�ŏt�G�J�g���̎�����v�ɂ����Ă��A���{�o�c�A�́u�ٗp�ҕ�V�����������v�Ƃ����J�����z�����f�ڂ��Ȃ��A�Ƃ����Ή����Ƃ����킯�ł���܂��B�i�������w������x��i�̓��v�����Ƃ��Ă͌f�ځj
�@�������Ȃ��炱��́A�����J���̎咣�����ꂽ�Ƃ������́A�ނ���A
���ŐV�̃f�[�^�ł́A���{�o�c�A���g���Ă����u�ٗp�ҕ�V�����������v�Ƃ����J�����z���ł���A�ቺ���Ă��܂����B
���u�t���͂��łɏI�������v�Ƃ��āA���{�o�c�A���]���A��������̃}�N���I�Ȗڈ��Ƃ��Ă����u���Y��������v��\�����Čf���Ă��Ȃ��ȏ�A�}�N���x�[�X�̘J�����z�����������Ƃ͈Ӗ����Ȃ��B
�Ƃ������f�ɂ��̂ł͂Ȃ����A�Ɛ�������܂��B
�@���{�o�c�A���g�p���Ă����u�ٗp�ҕ�V�����������v�Ƃ����J�����z���́A2001�N�x�ɂ�73.9���ł������A2002�N�x�ɂ�73.0���ɒቺ���Ă��܂��B73.0���Ƃ������l�́A�ŋ߂T�N�ԂłQ�ԖڂɒႢ�����ł��B�o�J�ϕ̂Ȃ��Łu�J�����z���̏㏸�v�̌��O���ĎO�ɂ킽���ď����Ă���Ȃ��ŁA���̂悤�ȃf�[�^���X�I�Ɍf�ڂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��킯�ł��B
�@������ɂ��Ă��A�{���㏸�X���������Ă���͂��̘J�����z���ł���ቺ���Ă���A�Ƃ������Ƃ́A���{�o�ςɂƂ��Ă���߂Ċ�@�I�ȏł���Ƃ����܂��B
�A�}�N���x�[�X�i�f�c�o�x�[�X�j�̘J�����z���͊����Œᐅ��
�����J���ł͏]�����A�ΘJ�҂ւ̕t�����l�̔z���̓x������]�����邽�߂̎w�W�Ƃ��āA
�����c�Ǝ҂��ٗp�҉�����e�����Ȃ��B
������̕t�����l�Ɍ������p�i�Œ莑�{���Ձj���܂܂�Ă���B
�Ƃ����ӂ��̏������N���A����A
�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o
�Ƃ����J�����z����p���Ă��܂��B���̘J�����z���̐��ڂ�����ƁA93�N�x�ɂ�67.2���������̂��A���̌�قڈ�т��Ēቺ�X�������ǂ�A2002�N�x�ɂ�63.1���ɒቺ�A���v�J�n�ȗ��̍Œᐅ���ƂȂ��Ă��܂��B���{�o�c�A�̌��O����u�����̉����d�����v�u�s�����̘J�����z���̏㏸�v�����z�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\�R�j
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) ���Y���������I�グ�ɂ������{�o�c�A
�@�f�t�����Ře�ɂ����ꂽ���Y�������
�@�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ł́A���{�o�c�A��70�N�ȗ��A����������ɂ�����o�c���̃}�N���I�Ȗڈ��Ƃ��Ă����u���Y��������v���f���Ă��܂���B
�@�u���Y��������v�Ƃ́A�P�l������̐l����̏㏸���i���F�菸�͊�{�I�ɂ͓��]�����Ȃ̂ŁA����Ɋ܂܂�Ȃ��j�A�}�N���x�[�X�ł����ƁA�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���������A�������I�ɍ��S�̂̎��������o�ϐ��Y���㏸���A���Ȃ킿�u�A�Ǝ҂P�l����������f�c�o�������v�Ɍ����������̂ɂ���Ƃ����l�����ł���܂��B
�@�@�@�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���������A�Ǝ҂P�l����������f�c�o������
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�O�q�̂悤�ɁA�}�N���x�[�X�̘J�����z�����C
�@�@�@�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o
�Ƃ���ƁA���Y��������ł́A���q�́u�A�Ǝ҂P�l����������f�c�o�������v�Ɍ������ĕω����A����̕ω��́u�A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o�������v�ƂȂ�܂��B
| ���q |
�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V |
�� |
�A�Ǝ҂P�l����������f�c�o�������ŕω� |
|
| ���� |
�A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o |
�� |
�A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o�������ŕω� |
�@���̂��ߕ������㏸���Ă���i�C���t���j�ꍇ�ɂ́A
�@�@�@���q�̑������@���@����̑�����
�ƂȂ��āA�J�����z�����ቺ���܂��B���Y��������́A�C���t���̎��ɂ́A�u�J�����z���ቺ�����v�Ƃ��č�p���܂��B
�@����A�������ቺ���Ă���i�f�t���j�ꍇ�ɂ́A���ڐ����������ł���A������������Ή�����قǁA���グ���������Ȃ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
�Ⴆ�ΐ��{�o�ό��ʂ���2003�N�x���ь����݂ł́A
�@�@�@�@�����f�c�o��������2.0��
�@�@�@�@�A�Ǝґ�������-0.1��
�@�@���@�A�Ǝ҂P�l����������f�c�o��������2.1��
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Y��������ɏ]���A2003�N�x�ɂ�2.1���̃x�A�i�菸�������j�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����������Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��킯�ŁA�f�t���̉��ł́A���Y��������͌o�c���ɂƂ��ėp�����A�ނ���L�Q�Ƃ����킯�ł��B
�A���{�o�c�A�͐��Y������������S�ɕ������ׂ�
�C���t���̎��ɂ́A�J�����z�������������ăC���t���̂������ׂċΘJ�҂ɉ������A�f�t���̎��ɂ͋@�\���Ȃ��悤�ȁu���Y��������v�́A���������u�����v�ȂǂƂ����ɒl���Ȃ��A���{�o�c�A�̂��s����`���̂��̂Ƃ�����ł��傤�B����A�o�J�ϕł͈�،��y���Ă��܂��A�u2004�N�ŏt�G�J�g���̎�����v�ł́A���������f�ڂ���Ă��܂��iP.60�j�̂ŁA�C���t���ɂȂ�����A������x�g�����Ƃ������Ƃł��傤���A���{�o�c�A���{���Ɂu�t���͂��łɏI�������v�Ǝv���Ă���Ȃ�A�܂��u���Y��������v���犮�S�ɏI���Ƃ��ׂ��ł��傤�B
�@�{���̓}�N���I�ɂ́A�D���ł��s���ł��A�C���t���ł��f�t���ł��A�J�����z�������ɕۂ悤�ȍl�����A���Ȃ킿�A
�@�@�@�ٗp�҂P�l�����薼�ڌٗp�ҕ�V���������A�Ǝ҂P�l�����薼�ڂf�c�o������
�Ƃ���t���Y��������i���t�����l���Y��������j�ɑ������l����肪�A�]�܂����Ƃ����܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
�Q�D����̓����ƒ��~��
(1) ����͊ɂ₩�ȉ
�@�����ȁE�ƌv�����ɂ���đS���E�ΘJ�Ґ��т̏����Ă݂�ƁA����x�o�̖��ڑ������́A2002�N10�`12�����ȍ~�A�O�N��Q�`�R���̃}�C�i�X�Ő��ڂ��Ă��܂������A2003�N10�`12�����ɂ́A��0.2���Ƀ}�C�i�X�����k�����܂����B
�@���������A2003�N�P�`�R�����ɑO�N�䁢5.9���Ƃ����啝�ȃ}�C�i�X���L�^���Ă����̂��A���̌�A����ǂ��ă}�C�i�X�����k�����A10�`12�����ɂ́�0.8���ɉ��P���Ă���Ƃ����A�������̉��P���A�傫����^���Ă�����̂ƍl�����܂��B�i�}�\�S�j
�@���{�o�c�A���u2004�N�ŏt�G�J�g���̎�����v�̂Ȃ��ŁA
����������N����Ƃ̔����L�����Ƃ��{�i�I�Ȑݔ������̉̂��߂ɂ͕K�v�ł���A���݂̉������ǂ��Ȃ��Ă������͏���̓�������������Ƃ����悤�B�iP.23�j
�Ǝw�E���Ă��܂��B�o�c���͂�����������オ��������ӗ~���A���Ȃ��Ƃ���₳�Ȃ��悤�ȁA�Ή����Ƃ��Ă������Ƃ��s���ƂȂ��Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�o�Y�Ȃ̏��Ɣ̔����v�ł��A�����Ɣ̔��z�̑������́A2003�N�S�`�U�����ɑO�N�䁢2.6���������̂��A�V�`�X������2.3���A10�`12������1.0���ƃ}�C�i�X�����k���X���ƂȂ��Ă��܂��B
�@�Ƃ�킯�����ԏ����Ƃ́A2003�N�N���Ɉꎞ�O�N����ƂȂ��Ă��܂������A�X���ȍ~�̓v���X�ɓ]���A12���ɂ�9.4�����ƂȂ��Ă��܂��B
�@��^�����X�̔��z�i�����X�j�́A�ˑR�������������Ă��܂����A����ł�2003�N�V�`�X�����ɑO�N�䁢4.2���ł������̂��A10�`12�����ɂ́�3.2���ɁA�}�C�i�X�������k�����Ă��܂��B�i�}�\�T�j
(2) �ϋv������ɑ���x�o
�@�����ȁE�ƌv�����̋ΘJ�ҁE�����сi�P�g���т��܂ށj�ɂ��āA�ϋv������ɑ���x�o�i���ځj�̏����Ă݂�ƁA2002�N10�`12�����A2003�N�P�`�R�����ɂ͑O�N��X����̑傫�ȃ}�C�i�X�ƂȂ��Ă��܂������A���̌�͂S�`�U������6.1�����A�V�`�X������9.7�����Ƒ啝�ȑ����������Ă��܂��B
�@2003�N�x�㔼���i�S�`�X�����j�ɂ��āA�ϋv������ɑ���x�o�����������ɐ�߂銄�����A�N���ܕ��ʊK���ʂɎZ�o����ƁA�ł��N���̏��Ȃ���P�ܕ��ʂł�3.5���A���ɏ��Ȃ���Q�ܕ��ʂ�3.5���Ȃ̂ɑ��A��R�ܕ��ʂł�5.4���A��S�ܕ���4.7���A��T�ܕ���4.4���ƂȂ��Ă���A�N���̍����ق��őϋv������ɑ���x�o�̊����������ɂ���܂��B�i�}�\�U�j
�@���Ϗ�����i����x�o�̉��������ɐ�߂銄���j�͏����̒Ⴂ���т������A�����̍������т��Ⴍ�Ȃ�X���ɂ���܂����A�ϋv������ɑ���x�o�̊����́A�T���č������ґw�̂ق��������X���ɂ���܂��B2003�N�x�㔼���́A���̌X�����Ƃ��ɂ͂�����o�Ă��Ă���Ƃ����܂��B
�@���ܔ��^�e���r��A�c�u�c���R�[�_�[�A�T�C�N�����|���@�A��������@�A�^���N�Ȃ�����g�C���ȂǁA���@�\�E���i���̐V���i�����X�Ɣ�������A����҂̍w���ӗ~�͏]���ɂȂ����܂��Ă��܂��B�������ґw�ɂ����đϋv������x�o�̔䗦�������Ȃ��Ă���̂́A���������w���ӗ~�f���Ă�����̂ƍl�����܂����A�������w���ӗ~�͍������ґw�Ɍ�������̂ł͂Ȃ��A��������r�I���Ȃ����тɂ����Ă��A�������L�т�A���������ϋv������ɑ�����v���A�܂��܂��L����������čs�����Ƃ����҂���܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) ���~���̒ቺ
�@�����̃}�C�i�X�̕��A���~���������Ă���
�@�ߔN�A�}�N���x�[�X�i�f�c�o�x�[�X�j�Ō����ƌv���~���̒ቺ���������ɂ���܂��B�������}�C�i�X�ɂȂ��Ă��邽�߁A�����̃}�C�i�X�̕��A���~�����炵�Ă��邱�Ƃ����~���ቺ�̌����ł��i����̏����ƕ��q�̒��~�����z�Ō���A���~���͒ቺ���܂��j�B�{���A���~�͓����̌��ł���A�킪���o�ς̐��ݐ����͂ɏd��ȉe����^������̂ł��B���~���̒ቺ�́A�킪���̒����I�Ȕ��W�ɂƂ��āA����߂ėJ�����ׂ����ԂƂ��킴������܂���B
�@�킪���̂f�c�o�x�[�X�̉ƌv���~���i�ƌv���~���ƌv���������j�́A97�N�x�ɂ�11.1���ł������̂��A�ȍ~�A�ቺ�X�������ǂ�A2002�N�x�ɂ�6.2���Ɣ����߂��ɂ܂Œቺ���Ă��܂��B98�N�x�ȍ~�̉ƌv���~�Ɖƌv���������̋��z�����Ă݂�ƁA99�N�x�������S�N�Ԃɂ����āA�ƌv���~�̌����z���A�ƌv���������̌����z�Ƃقڌ����������̂ƂȂ��Ă��܂��B�ƌv���������̌������ƌv���~�̌����A�����ĉƌv���~���̒ቺ�������炵�����Ƃ͖��炩�ł��B
�i�}�\�V�j
�t�e�i�����������́A2003�N11���ɔ��\�������|�[�g�̂Ȃ��ŁA
����Ƃ��ٗp������i�Ƃ��āA�����̍팸���]�ސE�҂̕�W�E���قƂ����������̌��������X�g�����A�����N�𒆐S�ɍs���Ă��邽�߁A���łɒ��~�̎��������n�߂���Ȃ��Ȃ������т̊��������܂�A��N��ɕK�v�Ȑ��������̊m�ۂ�����Ȃ��Ă���B
��15�`24�̎�N�w�ł͐V���̗p�̗}���ɂ���Ď��Ɨ����}�㏸�A�p�[�g�E�A���o�C�g�J���҂�A�����ӎu�͂�����̖̂��E�Ƃ������s����Ȍٗp�����ɂ���t���[�^�[�̑����Ƒ��܂��Ă��łɒ��~������ቺ�����Ă���B��N�w�ɂ����鏊���i���̊g��⎑�Y�`���̒x��́A�{�l�����邾���łȂ��A�킪���̌o�ϊ��͂�傫���j�Q���鋰�ꂪ����B�t���[�^�[���r�����琳�Ј��Ƃ��Ă̐E��͓̂�����߁A��N�w�ɂ����鏊���i���g��⎑�Y�`���̒x��͋߂������A���N�w�ɂ��L���邾�낤�B
�Ǝw�E���Ă��܂��B
�A�ƌv�͒��~�������A��Ƃ͒��~���߂�
�@�ʏ�̏ꍇ�A�ƌv�͒��~���߁i�����������~�������j�A��Ƃ͓������߁i���~���������������j�ɂȂ�̂����ʂł��B�}�N���o�ς̂����ł́A
�@�@�@�ƌv�̒��~���߁|��Ƃ̓������߁������Ԏ��{�f�Ս���
�Ƃ����W�ɂ���܂��B�Ƃ��낪����̕s���ł́A��Ƃ����~���߂ƂȂ��Ă��܂��܂����B98�N�x�ɂf�c�o�̓��v�J�n�ȗ����߂āA����Z�@�l��Ƃ����~���߂Ɋׂ�A99�A2000�N�x�͂��낤���ē������߂ɖ߂������̂́A2001�N�x�ɂ͍Ăђ��~���߂ɓ]���A2002�N�x�ɂ͉ƌv�̒��~���߁i11.2���~�j������A17.4���~�Ƃ������~���߂��L�^���Ă��܂��B�i�}�\�W�j
�}�\�X�́A��ʓI�ȃ}�N���o�ϊw�̋��ȏ��ɍڂ��Ă���o�ς̃t���[�z�̐}�ł��B��Ƃ͒�����z���̂������ŁA�ƌv�ɏ������x�����܂��B�ƌv�͏���������⒙�~�ɂ܂킵�܂��B�ƌv�̒��~�����{�s���ʂ��Ċ�Ƃɂ킽��A��Ƃ͂��̎����œ������ăr�W�l�X���s���A�Y�ݏo�����t�����l���A�Ăђ�����z���̂������ʼnƌv�ɏ����Ƃ��Ďx�����܂��B
�����������ꂪ�ʏ�̃t���[�z�ł���킯�ł����A��Ƃ����~���߂ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃ́A�����Ŏ����̗��ꂪ�l�܂��Ă���Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B���̌����̈ꕔ�ɂ́A���{�s��̋@�\������Ă���Ƃ������Ƃ����邩������܂��A��Ƃ����~���߂ł���ȏ�A��Ƃ̎苖�Ɏ����͂���킯�ŁA���{�s��̋@�\�s�S�������ł��Ȃ����R�ɂ͂Ȃ�܂���B��Ƃ��苖�̎����œ������邩�A�ƌv�ɏ����Ƃ��ĉ��A���炭���̗������s���A�o�ς̃t���[�z�͐��퉻����͂��ł��B��������Ύ��Y���i���㏸���A���Z�@�ւ̎��s�Ǎ����k�����āA���{�s�������ȏ�Ԃɋ߂Â����ƂɂȂ�܂��B
�}�\�X�@�o�ς̃t���[�z��

|
| �����o���F�q.�i.�S�[�h���u����}�N���G�R�m�~�b�N�X�v����o�ŁA1997�N |
|
<�y�[�W�̃g�b�v��>
�R�D���ʎ�`�̌���Ɩ��_
(1) ���ʎ�`�̓���
�@���ʎ�`�����̏�
�@�ߔN�A�����鐬�ʎ�`�̓������}���ɐi��ł���A�Z�\�E�ɂ��Ă��A�����������A�菸���x��p�~�����肷��Ⴊ�����܂��B
�@���{�J�������@�\�i���E�J�������E���C�@�\�j��2003�N�P���Ɏ��{�����u��Ƃ̐l���헪�ƘJ���҂̏A�ƈӎ��Ɋւ��钲���v�ɂ��A�u�������x�̕ύX���l���Ă����Ɗ����v��72.7���ɒB���A���̋�̓I�ȓ��e�i�����j�ł́A�u�����E���i��\�͎�`�I�ɉ^�p����v��67.9���A�u�l�Ɛт��{�[�i�X�ɔ��f������v��54.6���A�u��{���̐E�\���I�v�f�𑝂₷�v��44.5���A�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\10�j
�����V����2004�N�P���ɔ��\������v���112�Ђɑ���A���P�[�g�����ł́A���������S�Ј��ɂ��Ĕp�~������Ƃ�31.6���A���������p�~�����̂�14.3���A�p�~����������20.4���ƂȂ��Ă��܂��B
�@�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ɂ����āA���{�o�c�A�́A
���N���^�����͑��ΓI�ɒ����N�w�̒������������߁A�~���ȘJ���ړ��̖W���Ƃ��Ȃ��Ă���B���l�Ȑl�ނ��������A�J���҂̃��`�x�[�V���������߁A���Y�������コ���Ă������߂ɂ́A�N��E�Α��N���Ȃǂ̑��l�I�v�f�ɂ�镾�Q��r�����A�\�́E���ʁE�v���x�Ȃǂɉ������������x�ɐ�ւ��Ă����ׂ��ł���B�iP.61�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B�������Ȃ���A���ݓ������i��ł���A�����鐬�ʎ�`���u�J���҂̃��`�x�[�V���������߁A���Y�������コ���Ă����v���ʂ������̂��ǂ����́A���Ȃ�^��Ƃ��킴������܂���B
�A���ʂ���葽���������Ă���l�B�������͓��ł�
�@�����J���Ȃ̒����Z���T�X�ɂ����āA�����ƁA�j�q�A�呲�A�Ǘ��E�����E�Z�p�̕W���J���ҁi25�A30�A35�A40�A45�A50�A55�j�̏�������^�ɂ��āA��X�\���ʁi�Ώێ҂��ׂĂ����z�̏��ɕ��ׂāA�ォ��10���̂P�̂Ƃ���Ɉʒu����ҁj�̋��z���A98�N�ȍ~�A���̐��ڂ����Ă݂�ƁA35��45�ɂ��ẮA���������X������������̂́A���̑��̔N��ɂ��ẮA�������A�����X���������Ă��܂��B25�̏�������^�́A98�N�ɂ�26.9���~�������̂��A2002�N�ɂ�26.6���~�A30��35.8���~��33.9���~�A40��65.1���~��59.6���~�A50��78.1���~��76.3���~�A55��83.2���~��81.7���~�Ƃ�����ɁA���ꂼ��ቺ���Ă��܂��B�i�}�\11�j
���̌X���͑��Ɓi�]�ƈ�1,000�l�ȏ�j�������Ƃ��Č��Ă��قړ��l�ł�����A��X�\���ʂƂ����A��������r�I�����ΘJ�҂̒��������ł��ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ́A�����鐬�ʎ�`���i���̊ԁA���ʂ���葽���������Ă���ΘJ�҂̐l�B�ł���A�������������ł��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă���\���������Ƃ����܂��B
������u���ʎ�`�v���u���ʎ�`�v�Ƃ������̉��ɍs��ꂽ�P�Ȃ�����팸��ƂȂ��Ă��Ȃ����ǂ����A��Ɠ��ɂ�����`�F�b�N���s���Ƃ����܂��B
���t�{���s�����u�f�t�����̓��{��Ɓv�Ƃ����A���P�[�g�����ɂ��A��Ƃɐl����̈��k���@�����₷��i�����j�ƁA��P�ʂ́u�V�K�̗p�̏k���A�����v��62.8���ł����A��Q�ʂ́u���^�̌n�̌������v��58.5���ő����Ă��܂��B�i�}�\12�j
���{�o�c�A�́A���ʎ�`���u�J���҂̃��`�x�[�V���������߁A���Y�������コ���Ă����v���̂Ǝ咣���Ă��܂����A���ʂ���葽���������Ă���ΘJ�҂̐l�B�ł�����������ł��ɂȂ��Ă���A�ǂ����āu�J���҂̃��`�x�[�V���������߁A���Y�������コ���Ă����v���Ƃ��ł���ł��傤�B�Г��ł����ꕔ�̐l��������O�I�ɍ��������Ă����Ƃ��Ă��A�]�ƈ��S�̂̃��`�x�[�V���������܂�Ȃ���A��ƑS�̂̋Ɛт����߂Ă������Ƃ͂ł��܂���B
�u����15�N�ō������������v�ł��A
�����{�I�ٗp���s�̌��������A��N�����C�����������̂P���B�����N�̃��X�g����ڂ̓�����ɂ��A��{����{�[�i�X�̈����������o��������N�́A�T�[�r�X�c�Ƃ����A�x���ԏ�œ����Ă��A�����⏸�i�A�ٗp���ۏႳ��Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă���B��Ђ̏�i�́u�Ⴂ�Ƃ��̋�J�͔����Ăł�����v�Ƃ����B�m���ɁA�ꐶ�����n���ɓ����A�����A����Ȃ�̒n�ʂ������������Ƃ�����]������������ł���A�Ⴂ�����͋����������Ă����ς݂̋�J�ɑς��悤�Ǝv���ł��낤�B�������A���܂ǂ��̎�N�͎��オ�ς�������Ƃ�m���Ă���̂��B����Ȏ�N�����ς݂̋�J���}���悤�ɂȂ����Ƃ��Ă������͂Ȃ��B
�Ǝw�E���Ă��܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) ���ʎ�`�����ɍۂ��Ă̗��ӓ_
�@���ʎ�`�����Ŏw�E�������_
���{�J�������@�\��2003�N�P���ɍs�����u��Ƃ̐l���헪�ƘJ���҂̏A�ƈӎ��Ɋւ��钲���v�ɂ��A���Ј���67.2�����A���ʎ�`�I�Ȓ����̌n�ɂ��āA�u�^�������s���v�������́u���v�Ɖ��Ă���A���̗��R�i�����j�Ƃ��ẮA�u��i��Ǘ��҂��������]�����邩�킩��Ȃ��v��79.0���A�u�d���ɂ���Ă͔\�͂��������ɂ����v��51.0���ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�i�}�\13�j
2002�N�̌����J���ȁu�ٗp�Ǘ������v�ł��A�l���l�ې��x�ɂ��āA88.8���̊�Ƃ��u���x�E�^�c��̖��_������v�Ƃ��Ă���A��̓I�ɂ́i�����j�A�u���̈قȂ�d��������҂ւ̕]��������v��51.7���A�u�l�ێҌP�����s�\���ł���v��49.4���A�u�l�ۊ���s���m���͓��ꂪ����v��42.8���ȂǂƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\14�j
���c�L�j���i���E���叕�����j�́A�Љ�o�ϐ��Y���{�������{�����A���P�[�g���������ƂɁA���ʎ�`�I�������x�����ƃz���C�g�J���[�̓����ӗ~�ɑ��Ăǂ̂悤�ȕω���ł��邩�ɂ��āA
���ł��J���ӗ~�̏オ��m���������̂́A���ʎ�`�͓��������Ɏd�������̐����i�d�����e�̖��m���ƍٗʔ͈͂̌������j���s�����E��ł���B
���J���ӗ~�̌���m�����ł��Ⴂ�̂́A���ʎ�`���������A�d�������͕ς���Ă��Ȃ��E��ł���B
�����ʎ�`�Ƃ����u���v������p�ӂ��Ă��A�d���̒��g�₠������ς��Ȃ���ΘJ���ӗ~�͍��܂�Ȃ��B
�ƕ��͂��Ă��܂��i���{�o�ϐV��99�N12��30���j�B
�A���ʎ�`�������̓���
�����鐬�ʎ�`���삯�Ď����ꂽ��Ƃł́A
���K�n�f����������������B
���d���ւ̈ӗ~�A�v���Z�X�A���含�⎩���I�ȖڕW�ɑ��鐬�ʁA�ӗ~�I�ȖڕW�Ɍ����Ă̓w�͂Ȃǂ�]�����ڂɉ�����B
���`�[�����[�N�A�g�D�������ւ̍v���A�l�ވ琬�Ȃǂ̕]�����ڂ̔�d�����߂�B
����Ђ̊�{���j��b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j�ɑ�����H�x��]������B
�Ȃǂ̌�������i�߂Ă��܂��B�������Ȃ������ł́A���������������͋q�ϓI�ȕ]���̂ނ������������������Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���A���̓_�ł��J���g���̃`�F�b�N���܂��܂��d�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�@
�B���x�v�̊�{
�@�����E�������x�̌������ɂ������ẮA���x�v����щ^�p��̌���A�������܂ސ��x�^�p�ȂǂɁA�J���g�����ϋɓI�Ɋ֗^���A�����Ŕ[�����̍��������E�������x���\�z���邱�Ƃ��܂���{�ł��B�����āA���ꂼ��̎Y�ƁE�Ǝ�̓����ɉ����āA�ΘJ�҂̃����[�������߁A�J���ӗ~�̌���Ǝd����\�͔������K���ɕ]������A�����������m�ۂ��������E�������x�̊m������{�Ƃ��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@��̓I�ɂ́A
�����x�v�E�^�p������m�ł���A�����������m���������x�Ƃ��邱�ƁB
���]�����x�̓������E�[�����E���������m�ۂ���Ă��邱�ƁB
������̃`�F�b�N�@�\����ы����@�\���[�����Ă��邱�ƁB
���ΘJ�҂ɂƂ��ĕK�v�Ȑ��v��Œ���m�ۂ��ꂽ���x�Ƃ��邱�ƁB
�����ׂĂ̑g�������i�b�~�j�}��35��210,000�~���m�ۂ��邱�ƁB
���P�Ȃ鑍�z�l����팸��ړI�Ƃ������x�v�ƂȂ�Ȃ��悤�A�J���g���Ƃ��đ������Ǘ��ɗ��ӂ��邱�ƁB
�Ȃǂ��s���ȗv���ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
�S�D�����̍��۔�r
(1) �����̍��۔�r��������
�@�����J����2003�N�ɍs�������{�o�c�A�ɑ�����J�����ł́A�J�����z���ƂƂ��ɒ����̍��۔�r���傫�ȑ��_�ƂȂ�܂����B�u2003�N�Ōo�J�ϕv�ɂ����ē��{�o�c�A�́A�킪���̒����������u��i�����̂Ȃ��ł��g�b�v���x���v�iP.57�j�Ǝ咣���Ă��܂������A�����J���́A
�����{�o�c�A�������Ƃ��Ă���f�[�^�́A���{�́u���J�����Ԃ���������v�ƕēƂ́u�x���Ώێ��Ԃ���������v���r�������̂ŁA�u���J�����Ԃ�����v�ɑ����A�������@����O�̕�����������܂߂��u���J�����Ԃ�����l����v�Ŕ�r����A���{�̒��������͐�i�����Œ��ʂɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�Ǝw�E���܂����B
�@�u�x���Ώێ��Ԃ���������v�Ƃ����̂́A��G�c�ɂ����A����J�����ԂƏ���O�J�����Ԃ𑫂������̂ŁA��������J�����ԂƏ���O�J�����Ԃ̘a�ł���u���J�����ԁv�Ƃ̈Ⴂ�́A�u�x���Ώێ��ԁv�ɂ́u�N���L���x�ɂ̎擾���v���܂܂�Ă���A���l���傫���Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�u���Ԃ���������v�͎x�����ꂽ������J�����ԂŊ����ĎZ�o����̂ŁA�u�x���Ώێ��Ԃ���������v�́A�u���J�����Ԃ���������v�ɔ�ׂĕ��ꂪ�傫���Ȃ�A���ʂƂ��Ē����͒Ⴍ�Z�o����Ă��܂��܂��B�h�C�c�̂悤�ȍ��͔N���L���x�ɂ������̂ŁA���̉e���͂���߂đ傫���Ȃ�܂��B�i�R�����Q�Ɓj
| �x���Ώێ��Ԃ���������Ǝ��J�����Ԃ�������� |
�u�x���Ώێ��ԁv�Ƃ́A���{�I�ȕ\��������A�����ނ�
����J�����ԁ|�������Ύ��ԁ{���ߘJ������
�̂��Ƃł���B�x�������������z�́A
{���ԋ��~�i����J�����ԁ|�������Ύ��ԁj}�{�i���������~���ߘJ�����ԁj�{�ꎞ��
�ƂȂ�B���̑��z���A
�x���Ώێ��ԁ�����J�����ԁ|�������Ύ��ԁ{���ߘJ������
�Ŋ��������̂��u�x���Ώێ��Ԃ���������v�ł���B
����A�x�����z���A
���J�����ԁ�����J�����ԁ|�������Ύ��ԁ|�L���x�Ɏ擾���{���ߘJ������
�Ŋ���A�u���J�����Ԃ���������v�Ƃ������ƂɂȂ�B
���Ȃ킿�A�u�x���Ώێ��Ԃ���������v�́A�u���J�����Ԃ���������v�ɔ�ׂāA���ꂪ�u�L���x�Ɏ擾���v�����傫���Ȃ�̂ŁA���z���Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B |
�@�����J���̌��J�����ɑ�����{�o�c�A�̌����́A�O�q�̂Ƃ���A�u�f�[�^�̂Ƃ���́A�]�������т����l���̂��Ƃōs���Ă���v�Ƃ������̂ŁA����܂ň�т��āA���{�ƕēƂŒ�`�̈قȂ�f�[�^���g�p���A��r���Ă������Ƃ����߂ĔF�߂Ă���ɂ����܂���ł����B�U���ɍs���������J���Ɠ��{�o�c�A�̈ӌ������ł́A���{�o�c�A�����ǂ���A�u���v�f�[�^�́i�x���Ώێ��Ԃ�������������J�����Ԃ���������Ɋ��Z����悤�ȁj���H�͂��Ȃ����Ƃɂ��Ă���v�Ƃ̌�����������܂����B��`�̈قȂ�f�[�^�́A��`���ɉ��H���Ȃ���A��r�̑ΏۂƂȂ�Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��B�����������{�o�c�A���g�p���Ă�����{�̐����ƁE���Y�J���҂̒��������̃f�[�^�́A�u�����ΘJ���v�����A�����\����{���v���������Ƃɓ��{�o�c�A�ɂĐ��v�v�������̂ł�����A�u���H���Ȃ����Ƃɂ��Ă���v�Ƃ��������͖��炩�Ɍ��ŁA�o�J�ϕ͓s���̂悢�f�[�^��s���悭�g�ݍ��킹�āA���ׂĂ���ɂ����܂���B
(2) �����J���̎咣��������F�߂�2004�N�Ōo�J�ϕ�
�@�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ł́A�]�����l�́A���{�͎��J�����Ԃ���������A�ēƂ͎x���Ώێ��Ԃ������������ׂ��\�����������f�ځi�}�\19�@P.62�j���Ă��܂����A�u�e�����Ƃɓ��v�̎������قȂ邽�߁A�����Ȕ�r�͍���ł���v�Ƃ������߂��V���ɉ������܂����B�܂��{���ł́A�]���́u��i�����̂Ȃ��ł��g�b�v���x���v�Ƃ����\������A�u���E�̃g�b�v���x���v�ɉ��߂��܂����iP.60�j�B����́A
�����{�́u���J�����Ԃ���������v�ƕēƂ́u�x���Ώێ��Ԃ���������v�Ƃ���ׂĔ�r���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƁB
�����{�̒��������́A���o�ł����Ί֘e�E�������x���ł���A���o�E�S�̂ł́u�g�b�v���x���v�Ɉʒu����Ƃ��Ă��A���������Ŕ�ׂ�u�g�b�v���x���v�Ƃ͂����Ȃ����ƁB
��������F�߂����̂Ƃ����܂��B
�@�Ȃ��A�u2004�N�ŏt�G�J�g���̎�����v�ł́A���������̍��۔�r�̕\�iP.17�j�ŁA�u�e�����Ƃɓ��v�̎������قȂ邽�߁A�����Ȕ�r�͍���ł���v�Ƃ������߂������Ă��܂���B�J���g�������ڂ��Ă���o�J�ϕł́A�ꉞ�Ή�������̂́A��Ɍo�c�҂��J�g���̃}�j���A���Ƃ��Ċ��p����u������v�ł́A���߂����Ȃ��ł����Ƃ����̂́A�^��̎c��Ή��ł��B�J�g���ɂ����āA�o�c���������̍��۔�r�ɂ��Č��y���Ă����ꍇ�ɂ́A���̓_�ɂ��āA�\���ɐ������Ă����K�v������܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) ���J�����Ԃ�����̐l����
�@���{�o�c�A�������Ă�������̍��۔�r�̃f�[�^�Ɋ�Â��āA
�����J�����Ԃ�����ɑ�����B
�����������łȂ��A�@����O�̕�������������������Ԃ�����l����ő�����B
�Ƃ������H���s���ƁA���{��100�Ƃ��āA�A�����J��116.5�A�h�C�c��115.3�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�i�}�\15�j
��ʓI�Ɂu���{�͕���������̊����������̂ł́v�Ƃ����v�����݂�����܂����A���{�͎�v��i���̂Ȃ��ŁA�Љ�ۏ�W�̔�p�⋳��P����̔䗦���Ⴂ���߂ɁA�ēƂɔ�ׂĒ����i�������^���z�j�ɑ�������ȊO�̕���������̔䗦���Ⴂ���Ƃɗ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�i�}�\16�j
�Ȃ��A�u2004�N�ŏt�G�J�g���̎�����v�ł́A
���u��������^���P���~�ӂ���ƁA��P��7000�~�̑��z�l����̑����������B�iP.58�j
�Ǝw�E���Ă��܂����A����7,000�~�̂Ȃ��ɂ́A������������łȂ��A�ꎞ���⏊��O�������܂܂��킯�ŁA���{�ł́A����������ɑ��āA�ꎞ���⏊��O�����̔䗦�������ȏ�A������O�̂��Ƃł��B�Ⴆ�Έꎞ��������̏���������ɌJ������A�P��7,000�~�͑傫���ቺ���܂��B������O�̂��Ƃ��A�������ł��邩�̂悤�ɏ������Ă�̂́A������܂��t�F�A�Ƃ͂����܂���B
�@�܂��A�h�k�n�Ŕ��s���Ă���j�h�k�l�iKEY INDICATORS OF THE LABOUR MARKET�j�Ƃ��������ł́A�����ƁE���Y�J���҂́u���J�����Ԃ�����l����v���r���Ă��܂����A����ɂ��ƁA���{��19.59�h���ł���̂ɑ��A�m���E�F�[23.13�h���A�h�C�c22.86�h���A�f���}�[�N21.98�h���A�X�C�X21.84�h���A�x���M�[21.04�h���A�A�����J20.32�h���A�t�B�������h19.94�h���ȂǂƂȂ��Ă��܂��B���Ȃ��Ƃ���i���̂Ȃ��ł́A���{�̒��������̓g�b�v���x���Ƃ͂����܂���B�i�}�\17�j
(4) �t�����l������l����̍��۔�r
�@�בփ��[�g�Ŕ�r�����l������d�v�ł����A�����Əd�v�Ȃ̂́A�P�P�ʂ̕t�����l���ǂ̂��炢�̐l����ʼn҂��o�������A�Ƃ����t�����l������l����P�ʘJ���R�X�g�ł��B
�@���{�o�c�A���A��N�i2003�N�Łj�̌o�J�ϕɂ����āA
�����ۋ����ɂ��炳���Y�Ƃɂ����ẮA���l����̐���������Ƃ������ɉ����A�u���Y�P�ʓ�����̐l����v�Ƃ����������̕]�����d�v�ł���B�i���P�ʘJ����p�j�iP.39�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B
�o�J�ϕł́A2003�N�ł�2004�N�ł��A��v���̒P�ʘJ���R�X�g���f�ڂ��Ă��܂����A����ɂ��ƁA�����Ƃɂ��ẮA���Ȃ��Ƃ��h�C�c�A�C�M���X�́A�P�ʘJ���R�X�g���킪�����������ƂȂ��Ă��܂��B�܂��o�J�ϕł́A�����Ƃ̃f�[�^��99�N�̐��l�ł����A���T�ł���h�k�n�̂j�h�k�l�̍ŐV�Łi��R�Łj�ł́A2001�N�̐��l�����\����Ă���A����ɂ��A�Ɖp�����łȂ��A�����J���A�ق�̂킸���ł͂���܂����A�킪���������Ă���ɂ���܂��B
�@����A�n�d�b�c�̎�������Z�o���������Y�Ƃ̒P�ʘJ���R�X�g�́A���{��100�Ƃ��āA�h�C�c��129.3�A�A�����J��114.0�A�C�^���A��110.2�A�t�����X��102.5�ƂȂ��Ă���A��v���̂Ȃ��œ��{�̐l��������Ƃ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�i�}�\18�j
<�y�[�W�̃g�b�v��>
�T�D�J�����ԊǗ��ƃG�O�[���v�g
(1) ���ʎ�`�A�ٗʘJ�����ƘJ�����ԊǗ�
�@���{�o�c�A�́u2004�N�Ōo�J�ϕv�ɂ����āA
���J����@��̍ٗʘJ�����̈�w�̗v���ɘa��i�߁A����Ɏd���̐��ʂ��J�����Ԃ̒����ɔ�Ⴕ�Ȃ��J���҂��������Ă�����ӂ܂��A�A�����J�̃z���C�g�J���[�E�C�O�[���v�V�������x�̂悤�ȁA���̘J���҂ɂ͘J�����ԋK���̓K�p�����O���鐧�x�̑��������E���������߂���B�iP.37�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B
�@�����J���Ȃ�2002�N�Ɂu�ٗʘJ�����Ɋւ��钲���v���s���Ă��܂����A����ɂ��ƁA���Ɩ��^�ٗʘJ�����ł́A�����ɂ���ĘJ�����Ԃ��u�����Ȃ����A��Ⓑ���Ȃ����v�J���҂�19.9���ɒB���Ă���A�u�Z���Ȃ����A���Z���Ȃ����v��14.2���������Ă���ɂ���܂��B�܂����N��Ԃ��u�����Ȃ����A���������Ȃ����v�J���҂�12.7���ŁA�u�ǂ��Ȃ����A�����ǂ��Ȃ����v��4.6�������Ȃ�����Ă��܂��B�i�}�\19�j
�@�{���A�z���C�g�J���[�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���邢�͎d���̐��ʂ��J�����Ԃ̒����ɔ�Ⴕ�悤�Ƃ��܂��ƁA�����ď���O�������x�����悤�Ǝx�����܂��ƁA���悻�l�Ԃ���ΘJ�҂��A���N���ێ����A�ʏ�̌l�����A�ƒ됶���A�Љ���������邽�߂ɁA�J�����Ԃɂ͈��̘g���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�}���ɍL������鍑�ۘJ���K�i�r�`8000�ł́A�T�̘J�����Ԃ�����O�J�����܂߂�60���Ԃɐ������Ă���A������ĘJ�������邱�Ƃ͂ł��܂���B�r�`8000�̘J�����ԋK���́A�J�����Ԗ@�����G�O�[���v�g�i���O�j�����l�B�ɂ��Ă��A�G�O�[���v�g����܂���B�ٗʘJ�����ł��낤���G�O�[���v�g�ł��낤���A���悻�]�ƈ��̘J�����Ԃ́A��������ƊǗ�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�A��������2001�N�ɔ��\�����u�w�������̑��l���ƘJ�����ԓ��̎��ԁx�Ɋւ��钲�������v�ɂ��A�T�̎��J�����Ԃ�40���Ԉȏ�A45���Ԗ����̘J���҂́A�u�������Ԃ��K�v�Ȃ����Ƃ��v�҂�76.7���A�u���܂������ԂɐH�����ł���v��68.7���A�u�Ƒ��ƒc�R�̎��Ԃ��Ƃ��v��74.2���A�u�d���Ɋւ�������Ԃ��Ƃ��v��60.6���A�u�n��ł̊�������ۂ��ł���v��54.0���ȂǂƂȂ��Ă��܂����A����A60�`65���Ԃ̘J���҂́A�u�������Ԃ��K�v�Ȃ����Ƃ��v�҂�39.6���A�u���܂������ԂɐH�����ł���v��22.2���A�u�Ƒ��ƒc�R�̎��Ԃ��Ƃ��v��22.2���A�u�d���Ɋւ�������Ԃ��Ƃ��v��18.5���A�u�n��ł̊�������ۂ��ł���v��11.1���ƌ������Ă���ɂ���܂��B�i�}�\20�j
�����鐬�ʎ�`�̓�����ٗʘJ�����̊g��ɂ��A����O�J���ɉ����ď���O�������x���킸�A�d���̐i�ߕ����ΘJ�ҌX�l�̍ٗʂɈς˂�����ɐi�ނȂ�A��Ƃ͋ΘJ�҂��I�[�o�[���[�N�ƂȂ�A���N�Ȃ��A�l�����A�ƒ됶���A�Љ�����Ȃ�������ɂ��邱�ƂɂȂ�Ȃ��悤�A�]�v�ɘJ�����ԊǗ�����������s���Ă����K�v������܂��B�܂��A��ƂƂ��ċΘJ�҂̃G���v���C���r���e�B�����߂�Ȃ�A���R�A�G���v���C���r���e�B��g�ɂ��邽�߂̎��Ԃ��A�ΘJ�҂ɒ��Ȃ���Ȃ�܂���B
�Ȃ��A�{���͍ٗʘJ�����̏ꍇ�����ł͂���܂��A�ٗʘJ���������Ă���ꍇ�͂Ƃ��ɁA�N���L���x�ɂ̊��S�擾���ł���悤�ȕ�����m�ۂ��Ă������Ƃ��K�v�ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) �A�����J�ɂ�����G�O�[���v�g���x�̓���
�@�A�����J�ɂ�����G�O�[���v�g���x�̂���܂�
�@�A�����J�ɂ�����G�O�[���v�g�Ƃ́A�ꕔ�̐E��ɏ]�����A�����J����@�i�e�k�r�`�j�̏���O�����̎x�����K�肩�珜�O�i�G�O�[���v�g�j�����]�ƈ��̂��Ƃ������܂��B�E���̐�����A�������g�Ŏ��Ԃ��Ǘ����A���ʂŕ]������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@��̓I�ȐE��Ƃ��ẮA
�������ƁE�T�[�r�X�Ƃɂ�������͈̔͂̃R�~�b�V�����̔��E�A�c�ƐE�B
�����͈̔͂̃R���s���[�^�[���E�B
���^�]��A�^�]����A�ז��A�D���A�C���E�����H�B
�����K�͔_��Ōٗp�����_�Ə]���ҁB
�������ԃf�B�[���[�̔̔����A���i�H�A�@�B�H�B
���G�߁E���N���G�[�V�����]�ƈ��B
���o�c�����A�Ǘ��E�A���E�A�O���c�ƐE�̃z���C�g�J���[�A�E�G�b�W�łȂ��T�����[�Ōٗp�����z���C�g�J���[�B
�����̑��A�ƒ���J���ҁA�a�@�E�V�l�z�[���ŋΖ�����ҁA���K�͏����X�̏]�ƈ��ȂǁB
�ƂȂ��Ă���A99�N���_�Ōٗp�҂P��1,896���l�̂����A2,553���l���z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�g�ƂȂ��Ă��܂��B
�A�G�O�[���v�g���x���v
�@�{�N�P���A�G�O�[���v�g���x�̔��{�I���v���s���܂����B�G�O�[���v�g�̑ΏۂƂȂ邩�ǂ����ŁA�i�ׂ��p�����Ă��邽�߁A�v���̖��m����}�������̂ł��B
�@��ȓ��e�Ƃ��ẮA
���T��425�h���i�N��22,100�h���j�ȉ��̂��ׂĂ̏]�ƈ��́A�m���G�O�[���v�g�i����O�����K��̑Ώہj�ƂȂ�B�i���s�͏T��155�h���j
����G�O�[���v�g�E�����T������20���ȏ�s�����]�ƈ����m���G�O�[���v�g�Ƃ��鐧�x�́A�p�~����B�i�]���͏T��155�`250�h���̏]�ƈ��ɓK�p�j
���T��425�h������o�c�����A�Ǘ��E�A���E�ɂ��āA�G�O�[���v�g�ƂȂ�v�����A���m���E�ɘa����B
���d���̎��E�ʂɊւ�炸�A�N��65,000�h���ȏ�̃z���C�g�J���[�]�ƈ��́A�G�O�[���v�g�Ƃ���B
�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�@�A�����J�J���Ȃ́A����̉����ŁA�G�O�[���v�g����m���G�O�[���v�g�ɓ]������]�ƈ��ɂ��āA������̎��Ԃ�������������������āA����O�����Ƃ��킹�����x���z�����s�ǂ���Ɉێ�����A�Ƃ������Ƃ��ł���Ƃ��Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�P���̂������Ύ��Ԃ�����Ƃ��Ɍ����[�u����]�ƈ��ɂ��ẮA�G�O�[���v�g�ɂȂ�Ȃ��K��͂��̂܂܈ێ�����Ă��܂��B�J�����Ԃ��]�ƈ�������Ǘ����Ă��邩�ǂ����̔��f�������ł���ƍl�����܂��B
�B���{�̏Ƃ̈Ⴂ
�@����̉����ɂ���āA�G�O�[���v�g�̑Ώێ҂��啝�Ɋg�傷�邱�Ƃ��\�z����Ă��܂��B�������Ȃ���A���s�Ńm���G�O�[���v�g�ƂȂ��Ă���X�疜�l�̂����A���ۂɏ���O���������Ă���i���Ȃ킿�c�Ƃ�x���o�����Ă���j�ٗp�҂́A�P��100�`�P��200���l�i�����T�ɂ����āj�ɂ����܂���B�����̏]�ƈ�������P��I�ɏ���O�J�����s���Ă���킪���Ƃ̏̈Ⴂ�ɗ��ӂ��邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�܂��A���̂Ƃ�����P���i�݂�����̂́A������s�����c�Ƃ̑��݂͈ˑR�Ƃ��đ傫�Ȗ��ł���A�܂��N���L���x�ɂ̊��S�擾���i��ł��܂���B�J�����Ԑ��x���߂����ĉ������ׂ��傫�ȉۑ������Ă�����Ȃ��ŁA�G�O�[���v�g���x�̌o�c���ɂƂ��ēs���̗ǂ��Ƃ��낾�����܂�����Ȃ��悤�A�A�����J�Ɠ��{�̘J�����Ԗ@���̑���A�J�����Ԃ̎��Ԃ̈Ⴂ�ɂ��āA����ɗ�����[�߂Ă����K�v������܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
�U�D���l�Ȍٗp�`��
(1) ���l�Ȍٗp�`�ԂƋϓ�����
�@�ٗp�`�Ԃ͌l�̑I�������
�@�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ł́A
���A�ƌ`�Ԃ̑��l���͂���10�N�ԂŒ����ɐi�W���Ă����B���̗���͍���������Ă����Ɨ\�z����A���̌������ӂ܂�����ŁA���l�ȓ���������Ƃ̐��Y������Ə]�ƈ��̖����x�̌���ɂ����Ɍ��т��Ă������ɂ��āA�J�g���\���ɘ_�c���A���H���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l�͎����̐������ɍ�������������I�сA��Ƃ͌l�̗͂��\���ɔ����ł���g�D�������Ă����B�l�����x�́A���������J�g�o���̃j�[�Y�����A�x��������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�iP.35�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B�����ŏd�v�Ȃ̂́A�u�l�͎����̐������ɍ�������������I�сA��Ƃ͌l�̗͂��\���ɔ����ł���g�D�������Ă����v�Ƃ����Ƃ���ł���܂��B��ƂƂ��āA�l�X�ȏA�ƌ`�ԂɑΉ��ł���悤�ɂ��Ă������Ƃ͂���߂ďd�v�ł����A�ǂ̂悤�ȏA�ƌ`�Ԃ�I�����邩�́A�����܂ł��l�̑I�������ɂȂ���A�u�����̐������ɍ������������v���u�l�̗͂��\���ɔ����ł���g�D�v������̋�_�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�����J���Ȃ�2001�N�Ɏ��{�����u�p�[�g�^�C���J���ґ������Ԓ����v�ɂ��A���Ј��ȊO�̘J���҂��A���̓�������I���R�Ƃ��ẮA�p�[�g�J���҂ɂ��ẮA�u���Ј��Ƃ��ē������Ђ��Ȃ�����v��21.1���Ɏ~�܂��Ă��܂����A���̑��i�p�[�g�ȊO�j�̔Ј���38.0���ɒB���Ă���A�Ј��Ƃ��ē����Ă��闝�R�̑�P�ʂ��߂�Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B�O����95�N�ɂ́A�u���Ј��Ƃ��ē������Ђ��Ȃ�����v�̓p�[�g�J���҂�13.7���A�p�[�g�ȊO�̔Ј���31.7���ł�������A�����Ƃ��}���ɏ㏸���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�i�}�\21�j
�@����A��ƃT�C�h�̗��R���猩�Ă݂�ƁA�p�[�g���ٗp���闝�R�́A�u�l�������������v��65.3���ɒB���A�O��95�N�����i38.3���j�̔{�߂��̔䗦�ɒB���Ă��܂��B���̑��i�p�[�g�ȊO�j�̔Ј����ٗp���闝�R���A�u�l�������������v��95�N��29.3���ɑ��A2001�N�ɂ�57.9���ƁA������{�߂��ɒB���Ă��܂��B�i�}�\22�j
�@���{�o�c�A��������������ŏ����Ă��A�ٗp�`�Ԃ̑��l���̖ړI���A����ł͐l����̕ϓ���ƍ팸�ɂ��邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B�����J���Ȃł́A�N��A�Α��N���A�Y�ƁA��ƋK�͂��ɑ������ꍇ�́A��ʘJ���҂ƃp�[�g�^�C���J���҂̒����i�����Z�o���Ă��܂����A2001�N�̔�r�ň�ʘJ���҂�100�Ƃ��ăp�[�g�^�C���J���҂�58.1�Ɏ~�܂��Ă���A������90�N��ȍ~�A�i���͊g��X���ƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\23�j
�A���{�o�c�A�͋ϓ������Ɍ�����
�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ł́A
�����������ɕ����̌ٗp�`�Ԃ���������ꍇ�ɂ́A�ٗp�`�Ԃɂ��J�������̊i�����͂Ȃ͂��������̂ƂȂ�Ȃ��悤���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�iP.47�j
�Ǝw�E�������ŁA�u�ʏ�̘J���҂ƃp�[�g�^�C���J���҂̋ϓ������v�ɂ��Ă͂���߂Č������ŁA�u�d���̖����E�v���x�̈Ⴂ�ɂ�鏈���̊i���������I�ɐ����ł��v��悢�A�Ƃ��Ă���Ɏ~�܂��Ă��܂��B�����������Ƃ�����A���{�o�c�A���ٗp�`�Ԃ̑��l�����咣����Ӑ}���A�����ς�l����̈��������ɂ��邱�Ƃ͖��炩�Ƃ��킴������܂���B���{�o�c�A�͐^��
�u�l�͎����̐������ɍ�������������I�сA��Ƃ͌l�̗͂��\���ɔ����ł���g�D�������Ă����v���Ƃ��߂����Ȃ�A���Ј��ƃp�[�g�^�C�����͂��߂Ƃ���Ј��̂��ׂĂɂ�
���āA�ϓ��ҋ������Ɍ������K�C�h���C����}�j���A���������ׂ��ł���܂��B�܂��A�ϓ������̊m���ƍ��킹�A�Ј����A�t���^�C�����Ј���Z���Ԑ��Ј��ւ̓]�g���I���ł���悤�A����������}���Ă������Ƃ��K�v�ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) ���̂Â���Y�ƂƑ��l�Ȍٗp�`��
�@�r�W�l�X�E���f���ƌٗp�`�Ԃ̂����
�@���{�o�c�A���咣����u�ٗp�̃|�[�g�t�H���I�v�Ƃ����l�����ɂ��A��������ٗp�͈ꕔ�̊����Ј��݂̂ł���A�Z�\�E�A��ʐE�A���E�͒Z���i�L���j�ٗp�ƂȂ��Ă��܂��܂��B
�i�}�\24�j
�@���������l�����́A���̂Â���Y�Ƃ̗��ꂩ�炷��ƁA��a�������邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B�������Ђƌ��ɂ��̂Â���Y�ƂƂ����Ă��A
������܂ł̎s��ɂ͂Ȃ��A�܂������V�������i�𑼎Ђɐ�삯�ĊJ�����邱�Ƃ͂��Ȃ��B���Ђ��J�����A�Z�p�I�Ɋm�����ꂽ���i���A���v�ɍ��킹�Đv���Ɉ����ŋ�������B
�����i�̑g�ݗ��Ă̓��W�����[������Ă���A���x�ȎC�荇�킹�Z�p�E�Z�\�͕K�v�Ƃ��Ȃ��B
�Ƃ����A����u�f���^�v�̃r�W�l�X�E���f���̊�Ƃ̏ꍇ�ɂ́A���{�o�c�A�̎咣����ٗp�̃|�[�g�t�H���I�^���L���ƍl�����܂��B
�@�������Ȃ���A
�����E�ōŐ�[�̐V���i�����ЂŊJ�����Ă���B
���邢�́A
�����@�\���i�G�ɑg�ݍ��킹�đg�ݗ��Ă邽�߁A���x�ȎC�荇�킹�Z�p�E�Z�\���K�v�Ȑ��i�i���C���e�O�����Ȑ��i�j�����Ă���B
�Ƃ����悤�ȃr�W�l�X�E���f���̊�Ƃ̏ꍇ�ɂ́A�Z�\�E�A���E�ɂ��Ă��A��������ٗp����{�Ƃ��āA���x�n���̋Z�p�E�Z�\�A���邢�͌���̏���m�b�A�m�E�n�E�Ȃǂ�~�ς��A�O���ɗ��o���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ɕK�v�ł��B
�@�Ȃ��A�f���^���A�V���i�J���^���A�C���e�O�����^���ɂ��ẮA�ǂꂪ�D��Ă���Ƃ��A�������Ƃ��A�]�܂����Ƃ��A�����������l���f���܂ނ��̂ł͂Ȃ��A�P�Ƀr�W�l�X�E���f���̗ތ^�������Ă���ɂ����܂���B�܂��V���i�J���^�̊�Ƃ́A�������C���e�O�����^�ł�����A�܂��V���i�J���^�̊�Ƃł����Ă��A�f���^�̏��i�Y���Ă���ꍇ�������ȂǁA�����ɋ敪�ł�����̂ł͂���܂���B
�A�G�N�Z�����g�E�J���p�j�[�́u�l�v���d�������o�c
�@�o�ώY�ƏȂł͌��݁A�u�\�����v10�N�̑����ƍ���̓W�]�@�`�V���{��`�r�W�����Ɍ����ā`�v�̌�����Ƃ�i�߂Ă���Ƃ���ł����A
�����{���\����G�N�Z�����g�E�J���p�j�[�̌o�c�҂��Nj������ƃ��f���́A�]�ƈ��̎匠���d�����A�����ٗp��ڕW�Ɍf����X���������B
�������J�����d�������Ƃł́A���Ј��䗦�������A�ٗp�������x���x���B
�����ʎ�`�����Ă��A�u��l�ЂƂ�̔\�͂����������Ƃ������͋C�v�Ɓu�d�����e�̖��m���v�A�����āu�\�͊J���@��̊m�ہv���Ȃ���A�������ĘJ���ӗ~�͌��ނ���B
���ٗp��n�o���Ă����Ƃ́A�o�c�헪�Ƃ��Đl�ޓ������Ƃ��ɔM�S�ł���A�������悢�����łȂ��A�d���̂�肪���A�\�͔����̒��x�A�E��̐l�ԊW���D��Ă���X���ɂ���B
���A�����J�ł��A�����ٗp�Ɋ�Â��]�ƈ���̂̓����Ď����J�j�Y���̗L�������ĔF���������A�]�ƈ��d���̊�ƃ��f�������ڂ���Ă���B
����Ɖ��l�̑唼�́A���I���l�ł͑���Ȃ��u�����h��m�E�n�E�Ȃǂ̖��`���Y�ł���B���`���Y�̌��͐l�ނ̔\�͂ł���A���X�Ɗv�V�ݏo����Ƒg�D�̔\�͂ł���A�l�I���Y�Ƃ����ׂ����̂ł���B
�ł���A�u�l�I���Y�d���o�c�v�������A21���I�̊�ƃ��f���ł���Ƃ������͂�i�߂Ă��܂��B
�@�悭��ƌo�c�̃��f���Ƃ��āA���{�^�o�c�Ƃ��A�A���O���T�N�\���E���f���Ƃ������܂����A�G�N�Z�����g�E�J���p�j�[�ł���A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�i��Ɠ����j�̂������ɂ͂��Ⴂ�������Ă��A��Ƃ̍s���l�����͓̂��{�̊�Ƃ��A�����J�̊�Ƃ����قǕς��Ȃ��A��������ٗp���x�[�X�Ƃ��āA�]�ƈ��̔\�͂̒~�ς��d�����A����I�Ȕ\�͔����𑣂��A����𐳂����]�����A���Ƃł���A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���{�o�c�A��2003�N�S���A�u�Y�Ɨ͋����̉ۑ�ƓW�]�@�|2010�N�ɂ�����킪���Y�ƎЉ�|�v������A�u�Y�Ɨ͋����v�Ɍ����Ė��Ԃ����g�ނׂ��ۑ�������܂����B���Ԃ��哱����Y�Ɨ͋����̊�{�����Ƃ��ẮA
�@�Ő�[�Z�p�̊J���ƎY�Ɖ�
�A�V�����T�[�r�X�Ƃ̏o���E�g��
�B�����Y�Ƃ̌������E���t�����l��
���f���Ă��܂����A���������Ȃ��ŁA�u�o�J�ϕv�Ŏ咣����Ă���悤�ȁA�l����̈��������ɂ��ẮA�ЂƂ��Ƃ��G����Ă��܂���B
�@�u���E�I�Ȍ����J�����_����{�����ɂ����Č`���E���W�����A����𒆊j�Ƃ��ĐV���ȋZ�p�n�o�𐄐i���A���ʂƂ��Ă̋Z�p�E���i�����Ɖ�����v���Ƃɂ���āA�u�킪���̗D�ʐ����ێ��E�������Ă����v���Ƃ��߂����Ȃ�A���R�Ƃ�����ł��傤�B
�����A���ۋ����Ƃ́A���o��{�N�V���O�̂悤�Ɍ����������āu�ΐ�v������̂ł͂Ȃ��A�}���\���̂悤�ɋ��Z�҂����������������đ��������������u�����v�ł��B�u�ΐ�^�v�Ȃ�A���Ƃ��Β����Ƌ�������Ȃ�A�����Ƃ̐l�����r���傫�ȈӖ��������Ă��܂����A�u�����^�v�̏ꍇ�́A�l���������������Ƃ������Ƃ́A���ۋ�����A���{�̂��̂Â���Y�Ƃ̈ʒu���A�ǂ������Ă��鍑�X�̂Ƃ���܂ň����߂��Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B���{�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���̂������X�s�[�h�Œǂ������Ă��钆����V���H�ƍ��A���W�r�㍑��K���ŐU����āA�����܂Ő擪�𑖂葱����Ƃ������Ƃł���A���̂��߂��ғ��𗎂Ƃ��ăX�����Ȑg�̂ɂ���Ƃ������Ƃ͂������Ƃ��Ă��A���Ƃ������Ċ�b�I�ȑ̗͂܂Ŏ����Ă��܂�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��̗v�ł��B
�@�Ȃ��A�O�q�̓��{�o�c�A�́u�Y�Ɨ͋����̉ۑ�ƓW�]�v�ł́A�Y�Ɨ͋����̖ړI�Ƃ��āA�u�ǎ��Ȍٗp�@��̊m�ہv���f���Ă��܂��B�u�ǎ��Ȍٗp�v�Ƃ�������ɂ́A
���ٗp�`�ԂƂ��ẮA�t���^�C���܂��͒Z���Ԃ̐��Ј��A�����܂ŋΘJ�҂̑I���ɂ��A�ϓ��������m�ۂ��ꂽ�Ј��B
�����N���ێ����A�ʏ�̌l�����A�ƒ됶���A�Љ���������邱�Ƃ̂ł���J�����ԁB
�����Ȃ��Ƃ��N��ƂɕK�v�Ȑ��v����m�ۂ��A����ɓK���Ȑ��ʔz���̂Ȃ��ꂽ�����B
�Ȃǂ�Nj����Ă������Ƃ��K�v�ł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) ���{�ł́A���O���ɔ�ׂĐ��Ј��ȊO�̌ٗp�`�Ԃ̔䗦�������Ȃ��Ă���
�@�J�������E���C�@�\�����s���Ă���u�f�[�^�u�b�N���ۘJ����r2004�v�ɂ��A2001�N�ɂ�����A�Ǝ҂ɐ�߂�p�[�g�^�C�}�[�̔䗦�́A���{��24.9���ƂȂ��Ă���̂ɑ��A�C�M���X23.0���i2000�N�j�A�J�i�_18.1���A�h�C�c17.6���i2000�N�j�A�t�����X13.8���A�A�����J13.0���A�C�^���A12.2���Ɏ~�܂��Ă���A���{���f�V�������ō����L�^���Ă��܂��B�j�q�������Ƃ��Č��Ă��A�p�[�g�^�C�}�[�̔䗦�͂f�V�ō��ƂȂ��Ă��܂��B�u�p�[�g�^�C�}�[�v�̒�`�ɂ��āA���{�͏T���J��35���Ԗ����A���̍��X�͏T����30���Ԗ����ƂȂ��Ă��܂����A���{�ł́A�p�[�g�^�C���̘J�����Ԃ����Ј��ɔ�ׂĕK�������Z���Ԃł͂Ȃ����Ƃ��炷��A�����Ȕ�r�ł͂���܂���B�܂��A�����J�̃f�[�^�́A���ꂪ�A�Ǝ҂ł͂Ȃ��Čٗp�҂ł��̂ŁA���̍��X�������������߂ɏo�邱�ƂɂȂ�܂����A����ł����{���啝�ɒႭ�Ȃ��Ă��܂��B
�@2002�N�ɂ�����A�ٗp�҂ɐ�߂�e���|�����[�ٗp�҂̔䗦�́A���{��13.5���ɑ��A�t�����X14.1���A�J�i�_13.0���A�h�C�c12.0���A�C�^���A9.9���A�C�M���X6.1���ƂȂ��Ă���A�f�V�����Ńf�[�^�̂Ȃ��A�����J�ȊO�ł́A�t�����X�Ɏ����ō��������ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��A���̃f�[�^�ł́A���{�̒�`�́u���X�܂��͂P�N�����̌ٗp���Ԃ̎ҁv�ł���A�ꕔ�̔h���J���҂Ȃǂ������Ă��炸�A���̍��X�ɔ�ׁA�ނ����`�������Ȃ��Ă��܂��B�i�}�\25�j
�@�Ȃ��A�����ȁE�J���͒����ڍ��ʂɂ��A�ٗp�ґS�̂ɐ�߂�u�����E���K�ȊO�̌ٗp�ҁv�̊����́A2003�N�V�`�X�����ŁA��_�ыƂ�27.9���ƑO�N������+0.4�|�C���g�A���������Ƃ�18.9���œ�����+1.5�|�C���g�ƂȂ��Ă��܂��B�����ƈȊO�̔�_�ыƂł́A30.5���ƍ������ɂȂ��Ă��܂����A�O�N�����ɔ�ׂĂقډ����ƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\26�j
<�y�[�W�̃g�b�v��>
�V�D�i�b�~�j�}���ƎY�ƕʍŒ�
(1) �i�b�~�j�}���^��
�����O�̋���������f�t���̒������A����ɔ����ٗp�`�Ԃ̑��l���Ȃǂ̘J���s��̕ω��Ȃǂɂ���āA���������̒ቺ�X����Y�ƊԁE��ƊԂ̒����i���̊g�傪�i�s���Ă��܂��B�܂��A�d���̐��ʂ��d�������������x�ւ̉���ɂ���āA�l���Ƃ̒����̍��ق��ꕔ�Ŋg�債�Ă��Ă��܂��B
�����J���́A�����������ω��ɑΉ����āA�����Ȓ����������m�����A�����Y�Ƃɂ�������������̉��x����}��ׂ��A�i�b�~�j�}���^���𐄐i���Ă��܂��B
�u�i�b�~�j�}���i35�j�v�́A�����������v��̑��ʂ��l�����Ȃ�����������̉��x����}��ϓ_����A���v���������ԓ��𑍍��I�Ɋ��Ă���210,000�~�Ɛݒ肵�Ă��܂��B35�̋����Y�ƘJ���҂ł���A�Α��N���A�E���A�]���ɂ�����炸�A�����I�ɂ���ȉ����Ȃ����^���Ƃ��Ē��������m�ɉ��x�����Ă����܂��B
�܂��A��Ɠ��Œ��������ɂ��ẮA18�Œ������149,500�~�ł̒�����}���Ă����܂��B��Ɠ��Œ��������́A��Ƃɂ���������̉��x���ł���ƂƂ��ɁA�@��Y�ƕʍŒ�����\���̂��߂̍��ӂ����A���̐����ɂ��e����^������̂ł��B�@��Y�ƕʍŒ�����̎��g�݂Ƃ̘A�����������A���g�D�J���҂��܂߂������Y�Ƃœ����ΘJ�ґS�̂̒����̉��x����}�邱�Ƃ��d�v�ł��B
(2) �@��Y�ƕʍŒ�����̈Ӌ`�Ɩ���
�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ł́A
����Ƃ̒��������ɒ��ډe�����y�ڂ��͍̂Œ�������x�ł���B�i�o47�j
���Œ�����̋@�\�͒n��ʂ݂̂ŏ\���ł���A�Y�ƕʍŒ�����͔p�~���ׂ��ł���B�i�o47�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B
�@�������Ȃ���A�n��ʍŒ�������S�Ă̘J���҂ɓK�p���������̃i�V���i���~�j�}���ł���̂ɑ��āA�Y�ƕʍŒ�����́A�Y�Ƃ�E�킲�ƂɔN���Ɩ��Ȃǂ̓K�p�͈͂��߂�������u��I�J���ҁv�̍Œ�����ł���A�����Ƌ@�\���قȂ��Ă���A���Ƃ��u���㉮�v�Ƃ����悤�Ȕᔻ�͓I�͂���ł��B
���{�̒����\��������ƁA�d���̎��⓭�����Ȃǂ̈Ⴂ�f���āA�Y�Ƃ�E��ɂ��������ꂪ�`������Ă��܂��B�n��ʍŒ�����̑S�J���҂ɑ���e�����i�Œ�����̈����グ�ɂ���Ē��ڒ����������グ����J���҂̊����j�͂킸���P�����x�A����������ɑ��鐅���͂S�����x�ɉ߂����A�n��ʍŒ�����݂̂ł́A�����̎Y�ƂɂƂ��Ē����̉��x���Ƃ��Ă̋@�\���R�����ɂ���܂��B�Y�ƕʍŒ�����͓��{�̒��������ɓK�������������̂�������̉��x���Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă���A�Y�ƁE��Ƃ��Ƃ̒����i�����g�傷����ƂŁA���������̉��x����}��ϓ_��A����ɁA�Y�Ɠ��ɂ�������������̊m�ۂɂ��������Ȃ��V�X�e���ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��ߔN�A�ٗp�̗�������ٗp�`�Ԃ̑��l���ȂǁA�J���s�ꂪ�ω��������ŁA�d����E���v�f�Ƃ�����������̌X�������܂��Ă���A�Y�ƁE�E�킲�Ƃ̍Œ�����̏d�v�������܂��Ă��܂��B�Y�ƕʍŒ�����́A���g�D�J���҂ɂ��K�p�����A�킪���B��Ƃ������铖�Y�Y�ƘJ�g�Q���ɂ���������V�X�e���ƂȂ��Ă���A����Ƃ��p���E���W��}���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
�W�D60�Έȍ~�̏A�J�m��
�@�N���ƌٗp�̓����N����{
�@���m�̂悤�ɁA�{2004�N�S�����A���I�N���̖��z�x���J�n�N�62�Ɉ����グ���܂��B�����J���̑S�̏W�v�ɂ��A2003�N���_��3,618�g����1,219�g���ɂ����āA60�Έȍ~�̏A�J�m�ۂ��m�F�����Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B�������Ȃ���A���z�x���J�n�N������グ�ƂƂ��ɁA�A�J�m�ۂɂ��Ă�62�܂łƂȂ��Ă��邩�ǂ����ɂ��ẮA�ēx�`�F�b�N���Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�@�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ł́A65�܂ł̌p���ٗp���x�̋`�����ɂ��āA
�����������N�����x�ƌٗp�������N������͖̂��ł���A����͍���Ҍٗp��̐ӔC�ƍ���̃R�X�g�����ׂĊ�Ƃɉ������悤�Ƃ�����̂ŁA��ƌo�c�ɗ^����e���͂���߂đ傫���B�iP.39�j
�Ɣ������Ă��܂��B
�@�������Ȃ���A����������i�����ɂ����ẮA�N���x���J�n�N��������ޔN��ł��B�܂��N��x���J�n�N��肫�ł����āA�ΘJ�҂͂���ȍ~�������邯��ǂ��A�����]���Ă����ň��ނ���Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�܂���B�o�c����60�Έȍ~�̌ٗp�p���`�����ɔ�������̂́A�l��������k�������Ƃ������ꂩ�炷��A���������̍l����y�[�X�ł�肽���Ƃ����p�������邾�낤�Ǝv���܂����A�u�N�����x�ƌٗp�������N������͖̂��v�Ƃ����咣�́A���Ƃ��o�c���ł����Ă���O���킵�Ă���Ƃ��킴������܂���B
�A���ʎ�`�̂��Ƃł͒�N�͔N��ʂ̊댯��
�܂��A��N�Ƃ����l�������g�A���ۓI�Ɏ�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B���{�ł͂���܂ŁA���U�̐��ʂU�����ŕ�Ƃ����A������N���^�����ł��������߂ɁA���U�̐��ʂƐ��U���������������i�K�ʼn��ق���Ƃ�����N���x���������������Ď�����Ă��܂����B�������Ȃ���A�Z���̐��ʂ�Z���ŕ鐬�ʎ�`�ł́A��N���̑��݂ɂ��āA�����I�Ȑ������s�����Ƃ��ł����A�u�N��ɂ�鍷�ʁv�ɊY������댯�����傫���Ȃ��Ă��܂��B
�C�M���X�ł͂���܂ŁA��ʓI�ɒj����65�A������60�̒�N�����݂����Ă��܂����B�������Ȃ���A2000�N�ɍ̑����ꂽ�u�ٗp�ƐE�Ƃɂ�����ϓ��ҋ��Ɋւ���d�t�w�߁v�ɂ����āA�N��ɂ��ٗp���ʂ��ւ���@���̓��������߂��Ă��邽�߁A2003�N�V���A70�Έȉ��̑ސE�N����߂邱�Ƃ�A����𗝗R�Ƃ��Č��C�P���v���O�����̑ΏۂƂ��Ȃ����ƂȂǂ��֎~����A�u�A���`�E�G�C�W�Y���@�v���f�ՎY�ƏȂ���Ă���A2006�N�{�s�Ɍ����āA�������i�߂��Ă��܂��B
���������N�����z�x���J�n�N������グ�́A���I�N�����S��}�����邽�߂̂��̂ł��邱�Ƃ��Y����Ă��܂��B�N���ی����Ƃ��ĂƂ�����́A60�Έȏ�̕��ɂ���Ƃ̂��߂ɓ����Ă����������ق����ǂꂾ���悢���킩��܂���B���ʎ�`�ŏ�������A��ƂɂƂ��ĉ��̖��������Ȃ��͂��ł��B
�@�����ɁA��N�N��ƌ��I�N�����z�x���J�n�N��Ƃ̊Ԃɍ�������ȏ�A���̊Ԃ̐��v��́i��������ɍݐЂ�����Ƃ��ǂ����͂Ƃ������j��Ƃ��d���ȊO�ɂ͂���܂���B��N���}�����҂��ׂĂ��A���c�Ƃɓ]���邱�ƂȂǕs�\������ł��B���̏ꍇ�A���q��������i�݁A�Z�p�E�Z�\�̌p���E�琬����Ԃ܂�Ă���킪���ɂ����āA���ނ�������҂̕����܂��������Ⴂ�̃A���o�C�g�ȂǂɌg���̂��悢�̂��A����Ƃ����܂ł̌o���������E��Ŋ���̂��悢�̂��A�����͎����Ɩ��炩�ł��B�o�c�Ғc�̂́A�N�����z�x���J�n�N��܂ł̏A�J�m�ۂɂ��āA�ނ������U��A������Ƃ��w�����Ă������Ƃ������g���ł͂Ȃ��ł��傤���B<�y�[�W�̃g�b�v��>
�X�D�d���Ɖƒ�̗����x���|������琬�x�������i�@�ւ̑Ή�
�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ł́A
���j���Ƃ��Ɏd���Ɖƒ�𗼗��ł���Љ���߂������߂ɁA��Ƃ��ϋɓI�Ȗ������ʂ����Ă������Ƃ����҂����B�iP.38�j
�Əq�ׂĂ��܂��B
���q���̐i�W�́A�d���Ǝq��Ă̗����̕��S�������債�Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ��邱�Ƃ��w�E����Ă���A�����Ȃ���q���݈�Ă₷���ٗp���̐������i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A�����玙�E���x�Ɩ@��2003�N�S���Ɏ{�s�����ȂNJ��������}���Ă��Ă��܂��B
�Ƃ��ɁA2003�N�V���ɐ��������u������琬�x�������i�@�v�ł́A�e��Ƃɂ����āA�d���Ɖƒ�̗����x���̂��߂̐��x�����݂̂Ȃ炸�A�������̌��������܂߂���̓I�Ȋ����������߂��Ă���A301�l�ȏ���ٗp���鎖�Ǝ�ɑ��āA2005�N�S���ȍ~�A�u�s���v��v�̒�o���`���Â��Ă��܂��B�������Ȃ���A�s���v��̓��e�ɂ��ẮA�u�s���v�����w�j�v��������Ă�����̂́A���ꂼ���Ƃ̎���ɉ����č��肷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�u�s���v��v�́A�ΘJ�҂̃j�[�Y��I�m�ɔ��f���A�d���Ɖƒ�̗������}���鐧�x���m�����A�܂����x�����p���₷���E��Ƃ��Ă������Ƃ��ړI�ł��B���̂��߂ɂ́A�u�s���v��v�̗��āA���{�̂��߂̘J�g���c�̏��ݒ肷�邱�Ƃɂ���āA�J���g�����ϋɓI�ɎQ�����A�ΘJ�҂̈ӌ��f���Ă����K�v������܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
10�D�K���Ȑ��ʔz���Łu����́v�̋�����
(1) ����͂�ቺ��������{�o�c�A�̕��j
�@�o�c��������͂̒ቺ�Ɋ�@�ӎ�
�@���c�E���{�o�c�A��́A�u2004�N�Ōo�J�ϕv�́u�����v�ɂ����āA
���킪���o�ρE�Y�Ƃ̊�ՂƂȂ�ׂ�����̑����ɂ����āA�傫�Ȏ��̂�g���u�����������ł���̂́A�܂��ƂɗJ�����ׂ����ԂƂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A����������Ό���̐l�ޗ͂��ቺ���Ă��邱�Ƃ����O�����B��A�̎��̂̌����Ƃ��āA���X�g���ɂ���č��x�ȋZ�\��m�I�n����������̐l�ނ��팸���ꂽ���Ƃ��w�E����ӌ�������B���������w�E�������͌����Ɏ~�߁A�ڐ�̃��X�g���ɑ��邠�܂菫���I�Ȑl�ޗ͂̒~�ς����Ȃ��Ă��Ȃ����A���Ȃ̕K�v������̂ł͂Ȃ����B�o�c�����́A���̖���{���͎���̐ӔC�ł���Ƃ̔F�������ׂ��ł���B�iP.�U�j
����Ƃ��n�������t�����l�������̌����ƂȂ���̂ł���A���t�����l�o�c�Ƃ́A�]�ƈ��̍v���Ɍ��������������x�����A��Ƃ��K���ȗ��v���m�ۂ���o�c�Ƃ�������B��Ƃ̑����E�����̂��߂ɕt�����l�����߂�헪�𗧂āA���{���Ă��������J�g�o���ɂƂ��ďd�v�ȉۑ�ł���B�iP.�V�j
�Ǝw�E���Ă��܂��B
�܂��A�{�����́u��R���@����̌o�c�҂̂�����v�̂Ƃ���ł��A
���i��K�͂Ȏ��̂̕p���ɂ��āj���̖���P�ɋK���̖��Ƃ��ĂłȂ��A�u����́v���Ȃ킿����̐l�ޗ͂̒ቺ�̔��f�ł���ƁA��@���������ĔF������K�v�����낤�B��A�̎��̂́A���x�ȋZ�\��m�I�n����������̐l�ނ̌����A�ߓx�̐��ʎu���ɂ��]�ƈ��ւ̈��͂������ł͂Ȃ����A�Ƃ̎w�E������B�܂��A�����ٗp���s��ٗp�ێ��ɂ��Ċ�Ƃ̓w�͂��R�����ƁA�ᔻ����ӌ�������B����͂����߂邽�߂ɂ́A��V�⒦�������ł͕s�\���ł���A�o�c�����̈ӎ����v�Ȃ��ɂ́A���̍��{�I�����͂��肦�Ȃ��B�iP.66�j
���ٗp�ƘJ�������ɑ�����S���A�d���ɑ���[������g�D�ɑ���A���ӎ��{���邱�Ƃɂ���āA��Ɗ����ɑ���ӔC�����A�g�D���x���ƌX�̏]�ƈ��̃��x���̑o���ō��߂Ă����w�͂����߂ĕK�v�ƂȂ낤�B���ɍ���A������c��̐��オ�ސE���͂��߂邪�A�ނ�̋Z�p�E�Z�\������ɂ�����ƌp�������悤�Ȏd�g�݂��l���Ă������������Ă���B�iP.67�j
�Ƃ̎w�E������܂��B�����J���g���Ƃ��āA���������咣�ɂ͂Ȃ��٘_�͂���܂���B
�A����͂ɑ����@�ӎ��ƁA�o�c���̒��������j�Ƃ̃M���b�v
�@�������Ȃ������ł́A2004�N�̒���������ɑ��ẮA
���킪���̒��������͐��E�̃g�b�v���x���ɂ���A�Ƃ�킯����̂悤�ɕ������������Ă���ɂ����ẮA���ۋ����͂��ێ��E��������ϓ_������A���������̒������i�ق̉ۑ�ƂȂ�B���������̂Ȃ��ł́A���ڒl�Œ������㏸���Ȃ��Ă����������͏㏸���Ă���B�iP.60�j
���i��Ɠ��Łj�ꗥ�I�ȃx�[�X�A�b�v�͘_�O�ł���A�������x�̌������ɂ�鑮�l�I�������ڂ̔r�������������x�̔p�~�E�k���A����ɂ̓x�[�X�_�E�����J�g�̘b�������̑ΏۂƂȂ肤��B�iP.61�j
�ȂǂƎ咣���Ă��܂��B���������Ή��́A�o�J�ϕŁu����́v�ቺ�̌����Ƃ��Ă����Ă���A
���ߓx�̐��ʎu���ɂ��]�ƈ��ւ̈��́B
�������ٗp���s��ٗp�ێ��ɂ��Ċ�Ƃ̓w�̖͂R�����B
���ٗp�ƘJ�������ɑ�����S���A�d���ɑ���[������g�D�ɑ���A���ӎ��̌��@�B
���̂��̂ł���A�����o�J�ϕ̂Ȃ��ɂ�����M���b�v�̑傫���ɋ�������܂��B
�@��Ƃ̋����͂̌���ł���A�Z�p�E�Z�\�̌p���E�琬�A����̏���m�b�A�m�E�n�E�Ȃǂ̒~�ςƊ��p�Ɍ����āA����܂��܂��u�l�v���d�������o�c��W�J���Ă������Ƃ��s���ƂȂ��Ă��܂��B��Ƃ͋ΘJ�҂ɑ��A���肵���ٗp�A�K���Ȑ��ʔz���A�K�ȕ]���Ə����A�\���Ȕ\�͊J���̋@�����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�킪���̒��������́A��i���̂Ȃ��ł͒��ʂɂ������A�܂������������ቺ���Ă��܂��B�����┭�W�r�㍑�A�V���H�ƍ��Ƃ̐l����̊i���͑傫�Ȃ��̂�����܂����A���ۋ����͏�d�v�Ȃ̂́A�l����̊i�����k�����邱�Ƃł͂Ȃ��āA���̂������X�s�[�h�Œǂ������Ă��钆����V���H�ƍ��A���W�r�㍑��K���ŐU����āA�����܂Ő擪�𑖂葱����Ƃ������Ƃł��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
(2) ����������x�ƃx�[�X�A�b�v
�@�菸�͘J�������ɑ�����S���̌�
����������x���͂��߂Ƃ�������\���ێ����́A�ސE�҂̒������z��V���Ј��̒����ƍݐЎ҂ŕ��������d�g�݂ł���A�{���͒lj��I�ȃR�X�g�̔������Ȃ����̂ł��B�]�ƈ��̍\���ɂ���ẮA��ƂɁu�����o�����v���������܂����A�u�c��̐��オ�ސE�v���͂��߂�A�t�Ɋ�ƂɂƂ��č����ɂ��Ȃ�܂��B���Ƃ����x��͒���������Ȃ��A�Ƃ��Ă����Ƃł��A�T�O�Ƃ��Ă͒����\���ێ�����ے�ł��Ȃ��͂��ł��B�܂��A�Z���I�Ȑ��ʂ�Z���I�ɕ鐬�ʎ�`���i�߂ΐi�ނقǁA�N��ɉ����ĕK�v�Ȑ��v����m�ۂ��A�ΘJ�҂Ɂu�J�������ɑ�����S���v�������炷��ōł��d�v�ȗv�f�ł����������́A�d������Ȃ���Ȃ�܂���B
�A�x�A���l�ւ̐��ʔz���ɗp����̂͋؈Ⴂ
�܂��x�[�X�A�b�v�́A�l�l�ɑ�����グ�ł͂���܂���B�x�[�X�A�b�v�Ƃ́A
���o�ϐ����╨���㏸�A�J���s��Ȃǃ}�N���o�ς̓����B
�������̎Љ�I�ȑ���A�Y�ƊԁE�Y�Ɠ��̒����i�������B
���Y�Ɠ����B
����ƑS�̂̋ƐсB
�Ȃǂf���āA�����\���u��ĂɁv�����ς����Ƃł���A������u�x�[�X�v�A�b�v�Ȃ̂ł��B�o�ϐ����╨���㏸�A�����̎Љ�I�ȑ���A�Y�Ɠ����Ȃǂ́A�ΘJ�Ҍl�̐��ʂɂ���ĉe���������̂ł͂Ȃ��A�]���Ă����f���邽�߂ɍs���x�[�X�A�b�v���A�l�̐��ʂɕ邽�߂ɗp���邱�Ƃ͋؈Ⴂ�ł��B
��Ƃɂ���āA�o�c���̔��f�ŏd�_�I�ɒ��グ���������E���O���[�v������ꍇ�ɂ́A�ʌ���������̂������ł͂���܂����A�x�[�X�A�b�v�̂Ȃ��ōs���ꍇ�ɂ́A�܂��ꗥ�̔z�����o���_�Ƃ��������ŁA�x�[�X�A�b�v���̂����A��ƋƐтf���镔���̈ꕔ���A���������d�_�I�Ȕz���̌����Ƃ��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
������ɂ��Ă��A�u�ꗥ�I�ȃx�[�X�A�b�v�͘_�O�v�ȂǂƂ����咣�́A�x�[�X�A�b�v�̖{���𗝉����Ă��Ȃ��咣�ł���A���ꂱ���_�O�A�Ƃ��킴������܂���B
(3) �t���I���_�ɂ���
�@�u2004�N�Ōo�J�ϕv�ł́A
���J���g�������͍s�g��w�i�ɒ��������̎Љ�I���f�����Ӑ}���ē����Ƃ����u�t���v�͂��łɏI�������B�iP.63�j
����ƘJ�g���o�c���̕ω���o�c�ۑ�A���Ȃ킿�����E�J�����ԁE�ٗp��肩�瑽�l�ȓ������A�]�ƈ��X�l�̃L�����A�`���A�]�ƈ��琬�̂��߂̔\�͊J���A�����^���w���X�A��Ɨϗ��Ȃǂɂ��čL�͂ȋc�_���s�Ȃ��A��Ƃ̑����A�����͋����̕���c���A��������Ƃ����u�t���v�A�u�t�G�J�g���c�v�ւƕς��Ă������Ƃ��]�܂��B�iP.63�j
�Ǝ咣���Ă��܂��B�����E�J��������ٗp��肾���łȂ��A�l�X�Ȍo�c�ۑ�Ɋւ��āA�J�g�����c���Ă����Ƃ������Ƃɂ��ẮA�������łɑ����̑g���Ŏ��s����Ă��邱�Ƃł�����A�܂������٘_�͂���܂���B�������Ȃ���A���������J�g�̋c�_�́A�t�Ɍ�������̂ł͂Ȃ��A���R�̂��ƂȂ���ʔN�I�ɍs���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�Ƃ�킯�b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j���d�������Ȃ��ŁA�����Ƃ���v�ȃX�e�[�N�z���_�[�̂ЂƂł���J���g�����A��Ƃ̈ӎv����ɎQ�悵�Ă������Ƃ����߂��Ă���A�J�g���c�̏ꂾ���łȂ��A�b�r�q�W�̈ψ���ɘJ���g�����Q�����Ă������Ƃ��s���ƂȂ��Ă��܂��B
�@����A�J���g�������͍s�g��w�i�Ƀx�[�X�A�b�v�����߂ē����Ƃ����Ӗ��ł́u�t���v�͏���������̂ł͂���܂���B���������J���g���Ƃ́A�s��o�ς̂ЂƂł���J���s��ɂ����āA�J���͂̔�����ł����Ƃɔ�ׂāA�����ł���J���҂́u����̒n���v���ア���߂ɁA�c���ɂ���Ă����⊮���悤�Ƃ���g�D�ł��B�u����̒n���v������ɍ��߂邽�߂ɁA�Y�ƕʑg���A��Y�ʁA�����ăi�V���i���Z���^�[��g�D���A�������Čo�c���Ƃ̌��ɂ�����A�Ƃ��������́A����Ƃ��ς����̂ł͂���܂��A�܂��Ă���{�o�c�A����u�t���͏I�������v�Ȃǂƌ�����؍����͂���܂���B
�u����́v�ɐG�ꂽ�����ȂLjꕔ��O�͂�����̂́A�u2004�N�Ōo�c�J������ψ���v�̑S�̂𗬂���́A�Ђ�����l������팸����悢�Ƃ��������I�Ȏp���A遂�A���Ԃ�ł��B�����������{�o�c�A�̎p���́A�����̊�ƌo�c�҂݂̂Ȃ���̋C�����Ƃ͂܂������Ⴄ���̂��A�Ƃ����͍l���Ă��܂��B�ΘJ�Ґ����̈��S�E������x�[�X�Ƃ��āA�������̂Â���Y�Ƃ̊�Ջ�����}��A�킪���o�ς̐����O�������߂��A�����Đ��E�o�ςɍv�����邽�߁A�Y�ƘJ�g�͉����Ȃ��ׂ����A2004�N�����̘J�g���ɂ����āA�\���Ɍ�����[�߂Ă����K�v������܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
�P�D���̌o�ς̓���
(1) �f�c�o�̓���
�@�킪���o�ς́A�A�o��ݔ������̊g��A�l����̉����~�܂�Ȃǂɂ��A2002�N�t�ȍ~�i�C�ɓ]���A2003�N�N���A�����2003�N�Ăɂ�⌸���������̂́A�S�̂Ƃ��Ċɂ₩�Ȍi�C��ɂ�����̂Ɣ��f����܂��B
�@�킪���̖��ڂf�c�o�������́A2001�N�x�A2002�N�x�ƃ}�C�i�X�����������Ă��܂������A2003�N�S�`�U�����ɂ́A�X�l�����Ԃ�ɑO�N��Ńv���X�����i0.3���j�ƂȂ�܂����B�V�`�X�����ɂ͍Ăу}�C�i�X�����i��0.3���j�ɂȂ��Ă��܂����A�㔼���i�S�`�X�����j�Ƃ��ẮA���낤���ăv���X�����i0.0���j�ƂȂ��Ă���A���{�o�ό��ʂ��i2004�N�P��19���t�c����j��2003�N�x�ʊ��̎��ь����݂ł��A�R�N�Ԃ�̃v���X�����i0.1���j�������܂�Ă��܂��B
�@�l����́A99�N�x�ȍ~�S�N�A���Ŗ��ڃ}�C�i�X�����������Ă��܂����A2003�N�x�ɓ����Ă�����A�O�N��łS�`�U������0.4���A�V�`�X������1.5���ƃ}�C�i�X�����������Ă��܂��B���{���ʂ��ł��A2003�N�x���ь����݂́�0.7���ƂȂ��Ă��܂��B
�ݔ������́A2001�N�x�A2002�N�x�Ɩ��ڂŃ}�C�i�X�����������Ă��܂������A2003�N�S�`�U�����ɂ�5.1���A�V�`�X����2.9���ƌ����ɐ��ڂ��Ă��܂��B
�@�A�o�́A2002�N�S�`�U�����ȍ~�A�O�N��v���X�����������Ă���A2003�N�V�`�X�����ɂ�8.3���ƂȂ��Ă��܂��B2003�N�x�ɂ�4.5���̐����������܂�Ă��܂��B
�@�Ȃ������f�c�o�������́A2002�N�V�`�X�����ȍ~�A�O�N��v���X�����ƂȂ��Ă���A2003�N�S�`�U������2.3���A�V�`�X������1.9���ƂȂ��Ă��܂��B2003�N�x�ʊ��̎��ь����݂�2.0���ƂȂ��Ă��܂��B�i�}�\27�A28�j
(2) �i�C�w�W�̓���
�@��ʓI�ɂ́A�z�H�Ɛ��Y�w���̂����́u�o�w���v�̃}�C�i�X�����A�u�Ɏw���v�̃}�C�i�X�������������Ȃ��������i�C�ɓ]�����V�O�i���ł���A�t�Ɂu�o�w���v�̃v���X�����u�Ɏw���v�̃v���X�������������Ȃ��������i�C��ނ̃V�O�i���ł���Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B
�@2002�N�P�`�R�����ɂ́A�o�w�����O�N�䁢8.4���A�Ɏw������4.2���ƂȂ��Ă��܂������A���S�`�U�����ɂ́A�o�w������1.9���A�Ɏw������10.0���ƃ}�C�i�X�����t�]���A�i�C�ɓ]�������Ƃ������Ă��܂��B2002�N�V�`�X�����ȍ~�A�o�w���̓v���X�𑱂������A�Ɏw���̓}�C�i�X�𑱂��Ă��܂��B
�@2003�N�V�`�X�����ɂ́A�o�w����2.1���A�Ɏw������1.4���ƂȂ�A���̍������Ȃ菬�����Ȃ�܂������A����͈ꎞ�I�Ȍ����ŁA10�`12�����ɂ́A�o�w����4.9���A�Ɏw������1.3���ƁA�o�w��������Ԃ��Ă��Ă��܂��B�Ȃ��ł�12���́A�o�w��7.7���A�Ɏw����2.0���Ƒ啝�ɉ��P���Ă��܂��B�i�}�\29�j
�@�ݔ������̐�s�w�W�ł���@�B���v�i�D���E�d�͂����������j�́A2003�N�P�`�R�����ȍ~�A�O�N��v���X�ɓ]���܂����B�P�`�R����10.4���A�S�`�U����9.7���ɔ�ׁA�V�`�X�����ɂ�5.2���Ƃ��L�ї����݉����܂������A10����23.1���A11����13.4���ƂQ���̐L�ї��ƂȂ��Ă��܂��B�@��ʂł́A�����@�A�d�q�E�ʐM�@�B�A�H��@�B�A���H�ԗ��Ȃǂő傫�ȐL�т������Ă��܂��B
�@��R���Y�Ɗ����w���́A2003�N�P�`�R�����ȍ~�A�O�N��Ńv���X�̐L�ї��������Ă��܂��B�V�A�W���ɂ͈ꎞ�O�N����ƂȂ�܂������A�X���ȍ~�́A�Ăуv���X�Ő��ڂ��Ă��܂��B
�@���t�{�u�i�C�E�I�b�`���[�����v�́u�i�C�̌��f�i�������j�c�h�v�́A2003�N�T��������Ƃ��Ċɂ₩�ɏ㏸���A�X���ȍ~�͂ق�50���x�i�ǂ��Ȃ��Ă���Ǝv���l�ƈ����Ȃ��Ă���Ǝv���l���قړ����j�̉����Ő��ڂ��Ă��܂��B�i�}�\30�j
<�y�[�W�̃g�b�v��>
(3) �f�Ղ̓���
�@�����Ȃ̖f�Փ��v�ɂ��A2003�N�i��N�j�ɂ�����킪���̗A�o���z�́A�O�N��4.7�����ƂȂ�A�L�ї������݉����܂����B����ŁA�A�����z��5.0���ƗA�o�������L�ї��ƂȂ������߁A�f�Ս����͑O�N��3.6���̑����Ɏ~�܂�܂����B�������Ȃ���A�N�㔼�ɂ͗A�o�������ɐ��ڂ������A�A���̐L�ї����݉����Ă���A�f�Ս�����2003�N10���ȍ~�A�O�N��Q���̐L�ї��ƂȂ��Ă��܂��B
�@2003�N�S�̂ŁA�A�o����������ƁA����������33.2���̐L�ї��ƂȂ����̂��͂��߁A�C���h18.1���A�x�g�i��14.0���A�؍�12.6���A�^�C12.5���A���ؖ�����10.1���ȂǂƂȂ��Ă���A�A�W�A�����S�̂�12.9���̐L�ї��ƂȂ�܂����B���̂ق��A���V�A������72.5���A�I�Z�A�j�A������11.2���A�d�t������9.0���ȂǁA���ꂼ��啝�ȗA�o�g��ƂȂ��Ă��܂��B�悭�u�A�����J���݂̌i�C�v�Ƃ������Ƃ������܂����A���Ȃ��Ƃ����ڂ̖k�Č����A�o�́�9.7���i�A�����J�����́�9.8���j�̑啝�ȑO�N����ƂȂ��Ă��܂��B
�@�A�o�i�ڕʂɌ���ƁA��ʋ@�B�̂����̋������H�@�B�A���ݗp�E�z�R�p�@�B�A���M�p�E��p�p�@�B�A�ז��@�B�A�d�C�@��̂����̉f���@��A�d�C�v���@��A�����@��̂Ȃ��̕��ʋ@�Ȃǂ��O�N��Q���̑啝�g��ƂȂ��Ă��܂��B
�@���������ł́A��ʋ@�B��41.7���A�d�C�@�킪40.6���A�A���p�@�킪47.5���A�����@�킪57.4���ƁA�@�B�W�̊e�Ǝ킪�����݂S�`�T�������̏ƂȂ��Ă��܂��B�Ȃ������ɑ��ẮA�킪���͗A�����߂������Ă��܂����A�A�o�̍D���ɂ��A2003�N�ɂ͖f�ՐԎ���23.7���������܂����B�i�}�\31�j
�Q�D�����̓���
�@����ҕ����w���́A2003�N10���ɑO�N��0.0���ƂȂ�A99�N�W���ȗ��A�S�N�Q�J���Ԃ�Ƀf�t������E���܂����B�������Ȃ���A���N�H�i�̕��������Ȃǂɂ��A11���ɂ́�0.5���A12����0.4���A2004�N�P����0.6���i�s�敔�̃f�[�^����̐��v�l�j�ƁA�ނ���f�t�����������Ă���ɂ���܂��B
�@�������Ȃ���A�f�t���E�p�̖ڈ��ł���u�R�A�̏���ҕ����w�������N�H�i�����������v�́A2003�N10����0.1���ƃv���X�ƂȂ�A2004�N�P���ɂ͍Ăу}�C�i�X�ƂȂ��Ă�����̂́A��0.2���i�s�敔�̃f�[�^����̐��v�l�j�Ɏ~�܂��Ă��܂��B�i�}�\32�j
�@����A������ƕ����w���́A����܂ŏ���ҕ����w���������}�C�i�X�����傫���Ȃ��Ă��܂������A2003�N12���̑���ł́A�O�N�䁢0.1���܂Ń}�C�i�X�����k�����Ă��܂��B
�@����A�A�������w���́A2003�N�X���ȍ~�A�S�J���A���őO�N��}�C�i�X�ƂȂ��Ă���A12���̑���l�ł́A��3.6���ƂȂ��Ă��܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
�R�D�ٗp�̓���
�@�����������̑����Ă����ٗp����A�悤�₭���P�̒����������Ă���Ƃ���ƂȂ�܂����B2003�N12���̊��S���Ɨ���4.85���ƂȂ�A2001�N�U���ȗ��A�Q�N�U�J���Ԃ�ɂS����ɉ��P���܂����B�ň�������2003�N�P����5.53���ɔ�ׂāA0.68�|�C���g�̉��P�ƂȂ��Ă��܂��B�L�����l�{����0.78�{�ɉA�����93�N�T����0.79�{�ȗ��A����10�N�V�J���Ԃ�̍������ł��B�i�}�\33�j
�@���S���Ɨ��̉��P�̒��g�����Ă��A��J���͐l���̑������݉����A�A�Ǝ҂��v���X�ɓ]���Ă��܂��B�܂��u�Վ��فv�����łȂ��A�u��فv���������Ă��܂��B�i���F��J���͐l���́A�A�E������������߂��l���܂�ł���A��J���͐l������������ƁA���Ɨ��̕���ł���J���͐l�����������邽�߁A���S���Ɨ��͉��P����B����ɑ��ďA�Ǝ҂̑����́A���ۂɐE�ɂ������߂Ɏ��Ɨ������P�������Ƃ��Ӗ�����j
�@�Ȃ��A���Ɨ����S�̂Ƃ��đ啝�ɉ��P����Ȃ��ŁA�j�q��15�`24�A25�`34�ɂ��ẮA�ˑR�Ƃ��Ĉ����������Ă��܂��B<�y�[�W�̃g�b�v��>
�S�D���Z����ƈב�
(1) ���Z����̓����Ƃ킪���o��
�@�킪���o�ς͊ɂ₩�Ȍi�C�𑱂��Ă��܂����A���̔w�i�ɂ́A2001�N�X���̓��������e�������������Ƃ��āA����ȍ~�s��ꂽ�ʓI���Z�ɘa�̑啝�g�傪����܂��B
�@�}�l�^���[�x�[�X�̑������i�O�N��j�́A2001�N�V�`�X�����ɂ�10.4���ł������̂��A10�`12����15.6���A2002�N�P�`�R����27.8���ւƊg�傳��A�S�`�U������31.2���ɒB���܂����B�}�l�^���[�x�[�X�̐��ڂƌi�C�����w���i��s�w���j�̓������ׂĂ݂�ƁA�}�l�^���[�x�[�X���s�w�W�Ƃ��āA�قړ��l�̓����������Ă���A2001�N11���ɂ�0.0�������i�C�����w���i��s�w���j�́A2002�N�T���ɂ�83.3�܂ʼn��܂����B
�@���������l�̓����������A���o���ϊ�����2001�N�X���I�l��9,774.68�~�ł������̂��A10���ɂ͂P���~����A2002�N�T���ɂ͈ꎞ11,979.85�~�܂ʼn��܂����B���ڂf�c�o�����������ҕ����㏸�����A�}�C�i�X�����k�����Ă��܂����B
�@�������Ȃ��炻�̌�A����͍ĂїʓI���Z�������ߎp���ɓ]���A�}�l�^���[�x�[�X��2002�N�V�`�X�����ɑO�N��24.2���A10�`12������20.4���A2003�N�P�`�R�����ɂ�12.3���A�Ȃ��ł��R���ɂ�10.9���ɂ܂ŗ}������邱�ƂƂȂ�܂����B���������ʓI���Z�ɘa����̋}�u���[�L�ɉ����āA�C���N�푈��s�Ǎ������ɂ����̌o�ςւ̑Ō������O���ꂽ���ƂȂǂf���A�i�C�����w���i��s�w���j�́A2003�N�ɓ����50��ɒቺ�A�R���ɂ�25.0��15�J���Ԃ�̒Ⴂ�������L�^���邱�ƂƂȂ�܂����B���o���ϊ����������ɓ]���A2003�N�S���ɂ́A7,607.88�~�̃v���U���ӌ�ň��l���L�^���܂����B���ڂf�c�o�������͍Ăу}�C�i�X�����g�傷��ƂƂ��ɁA����ҕ����㏸�����}�C�i�X���̏k���Ƀu���[�L��������Ƃ���ƂȂ�܂����B
�@�R���ɂ͑�������ق��ޔC���A����V���ق��A�C�A����͍Ăы��Z�ɘa���g�傷��p���������A�}�l�^���[�x�[�X��2003�N�V�`�X�����ɂ�16.6���Ɉ����グ���A10���ɂ�17.4���i��������X�����Ђ̉e���������j�ƂȂ�܂����B���̂��߁A�i�C�����w���i��s�w���j�͂U�A�V����75�܂ŏ㏸�A�W���ɂ͂��ቺ�������̂́A10���ɂ�90.0�ƂȂ�܂����B�������X���ɂ�15�J���Ԃ�Ɉꎞ�P���P��~���A10������10,559.59�~�ƂȂ�܂����B
�@�������Ȃ���A�}�l�^���[�x�[�X�̐L�ї��́A11���ɂ�14.1���A12���ɂ�10.1���Ƌ}���ɗ}�������Ƃ���ƂȂ�܂����B�o�ς̈���̂��߂ɂ́A20���߂��}�l�^���[�x�[�X�������K�v�Ǝ��Z����Ă��邱�Ƃ���A���̐����ł͖��炩�ɕs���ł���A���̂��߁A�i�C�����w���i��s�w���j��11����50�ɒቺ�A������11�A12���ɂ͈ꎞ�P���~������܂����B�i�}�\34�A35�j
�@��q�̂悤�ɁA����͂���܂ŁA�����i�C���ǂ��Ȃ�Ƃ����Ƀ}�l�^���[�x�[�X���i���āA�ʓI���Z�������߂��s���Ƃ����u�X�g�b�v�E�A���h�E�S�[�v������Ƃ��Ă��Ă���A���ꂪ�i�C�̒��������Ȃ��v���ƂȂ��Ă��܂����B2003�N�H���ɂ́A�Ăѓ���́u�X�g�b�v�v����ɓ��ݍ����̂Ǝv���܂����A����ɑ��ẮA���{�Ȃ�тɖ��Ԍ����@�ւ���̋����ᔻ�����܂����B
�@�t�e�i�����ł́A2004�N�P���T���̌���i�C�ɂ����āA
���}�l�^���[�x�[�X�̎����ɂ���Ċ����̋}�����N����A��ƐS�������ҐS������C�ɗ₦���܂��A�i�C�g�匩�ʂ����C���𔗂���\�����ے�ł��Ȃ��B�בւɂ��Ă��A�N�������X�ɂ��Ăщ~�����}�i����\��������B
�����₪���ⓖ���a���c���̉�����30���~�A�����35���~�Ɉ����グ��悤�Ȓlj��ɘa���s���A�}�l�^���[�x�[�X�͍ĉ������A�בւ͉~�������ƂȂ�A�����ő傫�����������Ă��銔�����A��i�Ƌ��܂މ\���������B����ɂ́A���Ȃ����Z����^�c��]�݂����B
�Ǝw�E���܂����B
����́A2004�N�P��20���̐���ψ���E���Z�����ɂ����āA�u����̌i�C�̓���������Ɋm���Ȃ��̂Ƃ����|�v����A�����a���c���̖ڕW�l���A����܂ł́u27�`32���~���x�v����u30�`35���~���x�v�Ɉ����グ�邱�Ƃ�����A�ēx�A�u�S�[�v����ɓ]�����邱�Ƃ�錾���܂����B����̃}�l�^���[�x�[�X�ƌi�C�w�W�̓����𒍎����Ă������Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�i���j�ʓI���Z�ɘa���i�C�ɗ^����o�H�ɂ��ẮA�u2004�N�����̐��i�v���������������B
(2) �ב֑���
�@�~�����2003�N�H�ȍ~�}���ɏ㏸���A2004�N�P���ɂ͂P�h����105�~��ɒB���Ă��܂��B�v���U���ӌ�A�h�����E�~���ւ̓]�����}��ꂽ�t�v���U���ӂ܂�10�N�ԁA�����ċt�v���U���ӂ��炷�łɂX�N�߂����o�߂��Ă��邱�ƁA�킪���Ōi�C�������ƂȂ�A�������㏸���Ă��邱�ƁA�Ȃǂ��炷��A������x�̉~���͑z��͈͓̔��Ƃ����܂��B
�@���o�Y�ƐV����2003�N11���ɍs�����u�В�100�l�A���P�[�g�v�ł��A�u2004�N�R���܂ł̍��l�\�z�v�́A�u100�~�ȏ�A105�~�����v�Ƃ̉��ł�����43.9���ƂȂ��Ă���A���݂̐����ł���A���łɐD�荞�݂��݂̏ƂȂ��Ă��܂��B
�@�������Ȃ���A�ב֑���̋}���ȕϓ��Ɖߓx�ȉ~�����A�킪���A�o�Y�ƂɑŌ���^���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A���ۋ����̐��̋����ɂ��A�~����̈����}���Ă������Ƃ��K�v�ȏƂȂ��Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�����̐l�����ɂ��ẮA�킪������̋@�B�A�o���������Ă��邱�Ƃ�����A�K���������̈����グ���A�킪���o�ςɂƂ��čD�܂������ǂ����́A���ɂ߂��ނ��������ɂ���܂��B�������Ȃ���A���̂܂ܐl�������h���y�b�O�𑱂��Ă���A�����̌o�ϗ͂Ɛl��������Ƃ̘������܂��܂��g�傳��A�����o�ςƍ��ۋ��Z�̐��ɂƂ��ĕs����v�f�ƂȂ邱�Ƃ͔�������Ȃ����Ƃ���A�l�����̊��S�ϓ����ꐧ�ڍs�Ɍ����āA�킪���Ƃ��č��ۊ������ƒ������{�ւ̓������������߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂ���܂��B
<�y�[�W�̃g�b�v��> |
|
|