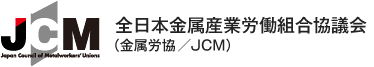�h�k�n���j�I�J����Ƃ́A���ЁE�c�̌��̎��R�A�����J���̋֎~�A�����J���̋֎~�A���ʂ̓P�p�̂S���w���܂��B �o�ς̃O���[�o�����A�s��o�ω��̐i�W�ɂ��A��Ƃ͍����̘g���z�������Y�A�̔��A���B���܂��܂������������Ă��܂��B����������Ɗ����́A���R�̂��ƂȂ�����̃��[���A�O���[�o���E�X�^���_�[�h�̉��ōs���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����A�J���E�ٗp����Ɋւ��Ă��A�����������[���͑��݂��Ă��܂��B �@�h�k�n�i���ۘJ���@�ցj�ł́A���ł�1977�N�ɁA���J�g���������āA�u�����Њ�Ƌy�юЉ��Ɋւ��錴���̎O�Ґ錾�i�O�Ґ錾�j�v�����肵�A�ٗp�A�P���A�J�������E���������A�J�g�W�Ȃǂ̕���Ɋւ��āA�����Њ�ƁA�{������ю��ꍑ���{�A�g�p�҂���јJ���Ғc�̂����s���ׂ��K�C�h���C�������肵�܂����B �@������98�N�ɂ́A��͂萭�J�g�̍��ӂ̂��ƁA�V���Ɂu�J���ɂ������{�I�����y�ь����Ɋւ���h�k�n�錾�i�V�錾�j�v���̑����A���ׂẲ������́A�h�k�n�ɂ����Ċ�{�I�Ȃ��̂Ƃ��ĔF�߂�ꂽ���A���Ȃ킿�A �@(a) ���Ђ̎��R�y�ђc�̌����̌��ʓI�ȏ��F�i��87�����A��98�����j �@(b) ������`�Ԃ̋����J���̋֎~�i��29�����A��105�����j �@(c) �����J���̎����I�Ȕp�~�i��138�����A��182�����j �@(d) �ٗp�y�ѐE�Ƃɂ����鍷�ʂ̓P�p�i��100�����A��111�����j �Ɋւ��ẮA��������������y���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ����Ă��A�h�k�n�̉������ł���Ƃ����������̂��̂ɂ��A���d���A���i���A��������`�������Ƃ�錾���܂����B �@�����Ɍf����ꂽ�����J���E�����J���̋֎~�A���ʂ̓P�p�A�c�����E�c�̌����̕ۏɂ��ẮA�u���j�I�J����i�R�A�E���[�o�[�E�X�^���_�[�h�j�v�ƌĂ�Ă���A�܂��ɘJ���E�ٗp����ɂ������{�I�ȃO���[�o���E�X�^���_�[�h�Ƃ���Ă��܂��B�d�v�Ȃ̂́A�u�O�Ґ錾�v�Ɏ�����Ă���悤�ɁA���j�I�J����m�����P�ɐ��{�����̐ӔC�ł͂Ȃ��A�O���[�o���Ȏ��ƓW�J���s����ƁA�g�p�Ғc�́A�J���g�����Ƃ��ɓw�͂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���܂��B<�߰�ނ�į���>
��1930�N�̋����J�����i��29���j ���{��y�ς� �@�������́A�u�����J���Ɋւ�����v�Ƃ����A���ׂĂ̋����J���̎g�p���A�ł������Z�����Ԃ̂����ɔp�~���邱�Ƃ�ړI�Ƃ������B���̏��ŁA�����J���Ƃ����̂́A�����̋��Ђɂ���ċ�������A�܂��A���炪�C�ӂɐ\���o�����̂łȂ����ׂĂ̘J���̂��Ƃł���B�����Ƃ��A���R����R���I�����̍�Ƃɑ���������@�ɂ���ċ��������J���A�����̒ʏ�̎s���I�`�����\������J���A�ٔ����̔����̌��ʂƂ��ċ��v�����J���A�ً}�̏ꍇ�A�Ⴆ�ΐ푈�A�ЁA�n�k�A�җ�ȗ��s�a���̑��̂悤�ȍЊQ�܂��͂��̂�����̂���ꍇ�ɋ��v�����J���A�y�ՂȒn��Љ�̘J���ł����Ēʏ�̎s���I�`���ƔF�߂���J���Ȃǂ͕�܂���Ȃ��B�����J�������S�ɔp�~�����܂ł̌o�ߊ��Ԓ��ɂ����āA��O�̑[�u�Ƃ��Ďg�p�����Ƃ��ɂ́A���̏��Ɍ��߂������ɏ]��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@���̏��Ɋ֘A���āA1930�N�Ɂu�Ԑڂ̘J�������Ɋւ��銩���v�i��35���j�Ɓu�����J���̋K���Ɋւ��銩���v�i��36���j���̑�����Ă���B <�߰�ނ�į���> ��1948�N�̌��Ђ̎��R�E�c�������i��87���j ���{��y�ς� �@�������́A�u���Ђ̎��R�y�ђc�����̕ی�Ɋւ�����v�Ƃ����B���ۘJ���@���͂����̑O���ɂ����āA���Ђ̎��R�̌����̏��F�����J�����������P���A���a���m�������i�ł���Ɛ錾���A�t�B���f���t�B�A�錾���A�\���ƌ��Ђ̎��R�͕s�f�̐i���̂��ߕs���ł���Əq�ׂĂ��邱�Ƃ��l�����č̑����ꂽ���́B���Ō��߂��Ă����Ȃ��Ƃ͎��̒ʂ�B�J���ҋy�юg�p�҂́A���O�̔F���Ȃ��ŁA����I������c�̂�ݗ����A�������邱�Ƃ��ł���B�J�g�c�́i�A���̂��܂ށj�́A�K������A���S�Ȏ��R�̂��Ƃɂ��̑�\�҂�I�сA�Ǘ��E���������߂邱�Ƃ��ł���B�s���@�ւ͂����̌����𐧌�������A���̍��@�I�ȍs�g��W������A�܂��A�J�g�c�̂����U������A�������~�������肵�Ȃ��B�J�g�c�͉̂E�̌������s�g����ɍۂ��Ă͂��̍��̖@���d���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����A���̍��̖@���́A���̏��ɋK�肷��ۏ���Q����悤�Ȃ��̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B <�߰�ނ�į���> ��1949�N�̒c�����E�c�������i��98���j ���{��y�ς� �@�������́A�u�c�����y�ђc�̌����ɂ��Ă̌����̓K�p�Ɋւ�����v�Ƃ����B �@�J���҂́A�J���g���ɉ������Ȃ��A�܂��͘J���g������E�ނ��邱�Ƃ��ٗp�����Ƃ�����A�g�����ł���Ƃ������R��J�����ԊO�A�܂��͎g�p�҂̓��ӂĘJ�����Ԓ��ɁA�g�������ɎQ�������Ƃ������R�Ȃǂʼn��ق��ꂽ��A���̑��̕s���v�Ȏ�舵�������ꂽ�肷��悤�ȍ��ʑҋ�����\���ȕی����B �@�J���Ғc�̋y�юg�p�Ғc�̂́A���̐ݗ��E�C�����s�E�Ǘ��ȂǂɊւ��āA���ꂼ�ꑊ�݂ɁA�����s�����Ɓi���ځE�Ԑڂ��킸�j���Ȃ��悤�ɕی����B���ɁA�J���Ғc�̂��g�p�҂܂��͂��̒c�̂̎x�z�̉��ɒu�����߂ɂ���s�ׁi�Ⴆ�A�g�p�҂܂��͂��̒c�̂Ɏx�z�����J���g���̐ݗ����i�E�J���g���ɑ���o����A���̑��̉����j�ɑ���\���ȕی������B�J�g�Ԃ̎���I���̂��߂̎葱���̔��B�◘�p�̏���̂��߁A�K�v������ꍇ�ɂ͓K���ȑ[�u���Ƃ�B �@�Ȃ��A���̏��́A���̍s���Ɍg���������̒n�ʂ���舵�����̂ł͂Ȃ��A���̌����╪���ɉe�����y�ڂ����̂ł͂Ȃ��ƒ�߂��Ă���B �@���̏��Ɋ֘A���āA1951�N�Ɂu�J������Ɋւ��銩���v�i��91���j�A�u�C�Ӓ���y�єC�Ӓ��قɊւ��銩���v�i��92���j���A1952�N�Ɂu��Ƃɂ�����g�p�҂ƘJ���҂Ƃ̋��c�y�ы��͂Ɋւ��銩���v�i��94���j���̑�����Ă���B <�߰�ނ�į���> ��1951�N�̓����V���i��100���j ���{��y�ς� �@�������́A�u���ꉿ�l�̘J���ɑ���j���J���҂̓����V�Ɋւ�����v�B���̏��͓���̉��l�̘J���ɑ��Ă͐��ʂɂ���ʂ��s�����ƂȂ������̕�V��^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ��߂����̂ł���B���͕�V�ɂ��Ē�`�������A���K�ł���ƌ����ł���Ƃ��킸�A���ڂ܂��͊ԐڂɎg�p�҂��J���҂ɑ��Ďx������V�ŘJ���҂̌ٗp���琶������̂��܂ށA�Ƃ���B �@��V��J���ɑ��Ēj�������Ɏx�����A�Ƃ����������m��������@�Ƃ��āA�@�����̖@�߁A�A�@�߂ɂ���Đݗ�����܂��͏��F���ꂽ�������萧�x�A�B�g�p�҂ƘJ���҂Ƃ̊ԂŒ������ꂽ�J������A�C�E�̊e��i�̑g�ݍ��킹�A���K�肵�Ă���B�X�ɁA�s���ׂ��d���Ɋ�Â��E���̋q�ϓI�]�������̏��̋K������{����̂ɖ𗧂ꍇ�ɂ͂���𑣐i����[�u���Ƃ邱�ƂƂ���B �@���̏��Ɋ֘A������̂Ƃ��āA1951�N�́u�����V�����v�i��90���j������B <�߰�ނ�į���> ��1957�N�̋����J���p�~���i��105���j ���{����y �@�������́A�u�����J���̔p�~�Ɋւ�����v�B���̏����y���鍑�́A���Ɍf�����i�A���ق܂��͕��@�Ƃ��Ă̂��ׂĂ̎�ނ̋����J����p�~���A����𗘗p���Ȃ����Ƃ����B a. a. �����I�Ȉ����������͋���̎�i�A�܂��͐����I�Ȍ����������͊����̐����I�E�Љ�I�������͌o�ϓI���x�Ɏv�z�I�ɔ����錩��������A�������͔��\���邱�Ƃɑ��鐧�� b. b. �o�ϓI���W�̖ړI�̂��߂ɁA�J���͂������p������@ c. c. �J���K���̎�i d. d. �X�g���C�L�ɎQ���������Ƃɑ��鐧�� e. e. �l��I�E�Љ�I�E�����I�܂��͏@���I���ʑҋ��̎�i �@���̏����y���鍑�͂܂��A�O�L�̂悤�ȋ����J���������S�ɔp�~���邽�߂ɕK�v�Ȍ��ʓI�ȑ[�u���Ƃ邱�Ƃ����B <�߰�ނ�į���> ��1958�N�̍��ʑҋ��i�ٗp�E�E�Ɓj���i��111���j���{����y �@�������́A�u�ٗp�y�ѐE�Ƃɂ��Ă̍��ʑҋ��Ɋւ�����v�B���̏��́A�ٗp�ƐE�Ƃ̖ʂŁA�ǂ̂悤�ȍ��ʑҋ����s���Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��K�肵�����̂ł���B�����ɂ������ʑҋ��Ƃ́A�u�l��A�畆�̐F�A���A�@���A�����I�����A�����I�o�g�A��n�ȂǂɊ�Â��čs���邷�ׂĂ̍��ʁA���O�܂��͗D��ŁA�ٗp��E�Ƃɂ�����@��܂��͑ҋ��̋ϓ���j������Q�����肷�錋�ʂƂȂ���́v���������A���ʂ̏�����K�v�Ƃ������̋`���ɂ��Ă̍��ʁE���O�܂��͗D��́A���ʑҋ��Ƃ݂͂Ȃ���Ȃ��B�܂��A���̈��S���Q���銈���ɂ��Đ����Ɍ��^���Ă���҂₱�̊����ɏ]�����Ă���҂ɑ��čs����[�u���A���ʑҋ��Ƃ݂͂Ȃ���Ȃ��B �@��y���́A���ʑҋ��p�~�̂��ߕK�v�Ȑ�����Ƃ�A���̐���𑣐i���Ă�����ŘJ�g�c�̂̋��͂����߁A�����ʑҋ��̖@���𐧒肵�A����v���i�߁A���̐���ƈ�v���Ȃ��@�߂̏�����p�~���A���߁E���s���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�֘A�����Ƃ��āA�����̊����i��111���j�������ɍ̑����ꂽ�B<�߰�ނ�į���> ��1973�N�̍Œ�N����i��138���j ���{��y�ς� �@�������́A�u�A�Ƃ��F�߂��邽�߂̍Œ�N��Ɋւ�����v�B�ߋ��ɍ̑����ꂽ������ɂ�����10�������肷�邱�̏��́A�����J���̔p�~�Ǝ�N�J���҂̘J�����������ړI�ɁA�A�Ƃ̍Œ�N����`������I���N��ƒ�߁A�����Ȃ�ꍇ��15��������Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Ƃ���B�������A�J���r�㍑�̏ꍇ�́A����������14�Ƃ��邱�Ƃ��F�߂���B �@��N�҂̌��N�A���S�A�����Ȃ�������̂���A�Ƃɂ��ẮA�Œ�N���18�Ɉ����グ����B�y�J���ɂ��ẮA���̏����̉��ɁA13�Έȏ�15�Ζ����̎҂̏A�Ƃ�F�߂邱�Ƃ��ł���i�r�㍑�̏ꍇ�ɂ�12�Έȏ�14�Ζ����j�B�����Ȃǂւ̏o���ɂ��ẮA��O���F�߂���B�K�p�͈͂́A���Ȃ��Ƃ������ƁA�^�A�A���݁A�_�ƓI��ƁA�H�Ƃ��܂ނ��̂Ƃ����B��ʋ���A�E�Ƌ���܂��͐�勳��̂��߂̊w�Z���̑��̌P���{�݂ɂ�����J���ɂ͓K�p����Ȃ��B �@�����̕⑫�I�����i��146���j�������ɍ̑�����Ă���B <�߰�ނ�į���> ��1999�N�̍ň��̌`�Ԃ̎����J�����i��182���j �O�c�@�ŐR�c�� �@�������́A�u�ň��̌`�Ԃ̎����J���̋֎~�y�ѓP�p�̂��߂̑����̍s���Ɋւ�����v�B1973�N�ɍ̑����ꂽ�Œ�N����i��138���j��⑫������̂Ƃ��āA18�Ζ����̎����ɂ��ň��̌`�Ԃ̎����J���̋֎~�y�ѓP�p���m�ۂ��邽�߂̑����̂����ʓI�ȑ[�u�����߂�B�ň��̌`�Ԃ̎����J���Ƃ́A���̂悤�ɒ�`�����B 1. �����̐l�g�����A���͕����ւ̋����I���p�A���z����܂ނ�����`�Ԃ̓z��J���܂��͂���ɗގ������s�� 2. ���t�A�|���m����A�킢���ȉ��Z�̂��߂̎����̎g�p�A�����A�� 3. �̐��Y�A�����ȂǁA�s���Ȋ����Ɏ������g�p�A�����܂��͒��邱�� 4. �����̌��N�A���S�A�����Ȃ�������̂���J�� �@��y���͌Y�����܂݁A���̌��ʓI�Ȏ��{�E�{�s���m�ۂ��邽�߂̑[�u���u����K�v������B�܂��A�����J���p��ɂ����鋳��̏d�v���ɔz�����Ȃ���A�\�h�A���������̉���A�Љ�A�Ɖe������̉A�����̊�b�������@��̊m�ہA���ʂȊ댯�ɂ��炳��Ă��鎙���֎�������L�ׂ邱�ƁA�����̓��ʂȏ̍l���Ƃ������ړI��B�����邽�߂Ɍ��ʓI�Ȏ����[�u���u���A���̌��ʓI�Ȏ��{���Ď�����K�ȋ@�\�̐ݒu�܂��͎w��A�ň��̌`�Ԃ̎����J����D��ۑ�Ƃ��Ĕp�₷�邽�߂̍s���v��̗��ĕ��тɎ��s�����߂��Ă���B�ň��̌`�Ԃ̎����J���̌��ʓI�ȋ֎~�E�P�p�Ɍ������������Ԃ̑����́E�x�����K�肳���B �@�����̕⑫�I�����i��190���j�������ɍ̑�����Ă���B <�߰�ނ�į���>
|