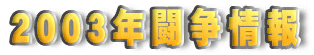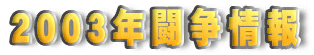|
2003年2月20日
全日本金属産業労働組合協議会
(IMF-JC)
金属労協は、本日午前10時より第3回戦術委員会を開催し、交渉に臨む基本姿勢を以下のとおり確認した。
1.金属労協は、2003年闘争を改革に向けた第一ステップと位置づけ、雇用と生活不安払拭のため成果の獲得につなげるべくJC共闘を推進している。
これまで、各産別は労使会議等を開催し、2003年闘争の要求実現にむけた主張を展開している。また各産別の指導のもと、各単組は2月中旬以降、順次要求提出を行い、団体交渉をスタートした。
本日までに、金属労協集計対象A組合66組合のうち、44組合が要求提出を完了した。要求提出したすべての組合が賃金構造維持分確保のための対応を進めており、1組合でベア要求を行っている。
JC全体としても、賃金構造維持分確保に向けて取り組みをすすめており、ベアについては各産別全体で500を超える組合が要求ないしその準備をすすめている。
2.われわれの要求に対して、経営側は、
①中国を始めとしたアジアの脅威が現実味を帯び、今後日本に生産拠点を残していけるかの局面に立たされている。
②グローバル競争を勝ち抜くためには、「新商品・新技術の開発」、「高品質なものづくり」はもちろん、コスト競争力を確保しなければならず、人件費を含めた固定費の圧縮は避けて通れない課題である。
③賃金構造維持を実施することも企業にとって大きな負担である。
などと、交渉の序盤から厳しい姿勢で臨んでいる。しかしながら、当然実施されるべき賃金構造維持でさえも否定するかのようなこうした経営側主張は、企業基盤の強化に向けて日々懸命に事業構造改革に取り組む組合員をないがしろにするものであり、これまでの労使関係を問い直すものといわざるをえない。
3.日本の金属産業は、他の先進主要国と単位労働コストについて比較すると、アメリカ、ドイツ、イギリス等いずれの国に対しても低水準になっている。また、金属産業の国際競争力強化のためには、高度熟練の技術・技能の力をさらに強化していくことが不可欠であり、人的投資の観点からも生産性の高さにふさわしい賃金水準・処遇が確立されなければならない。
また、日本経済の低迷は、個人消費の縮小による需給ギャップの拡大によるものであり、ここ数年の年間総賃金の減少に加え、賃金や一時金の更なる削減や年金・医療・介護などの将来不安に対する恐れが大きな要因となっている。デフレの加速によって日本経済を取り返しのつかない状態に悪化させないためには、企業労使がまず自らの努力によって雇用と生活の不安を払拭することが不可欠である。
そのため、賃金においては、賃金構造維持分の確保によって現在の賃金水準を維持するとともに、産業・企業の状況を踏まえて、ベアによって産業間・企業間の格差是正を行う組合についても、JC共闘全体で支えていく方針とする。また、一時金においては、年間総賃金の一部として安定的要素を確保したうえで、業績回復に応じて積極的に水準回復を実現することが不可欠である。さらに、JCミニマムの実現、最低賃金協定の締結、法定産業別最低賃金の取り組みなど、JCミニマム運動によって、金属産業の賃金水準の下支えを強化しなければならない。
わたしたちは、こうした観点から「JC共闘」の総力を結集し、この基本スタンスを最後まで堅持し、成果獲得に向けて全力を傾注し交渉を展開していくこととする。
4.一部の企業において、賃金水準改定の機をとらえて、交渉の前提となる賃金制度の改定を行おうとする動きがみられている。
しかし、春闘は、現行の賃金制度に基づく賃金水準の改定交渉を行う場であり、労働組合が現行制度に基づく賃金改定を交渉しようという時期に、交渉の基本となる賃金制度の改定を提案し、拙速な協議・合意を行おうとすることは、労使の信頼関係を損なうものと言わざるを得ない。賃金制度の変更は、通年的な労使協議の性格を持つものであり、2003年闘争と切り離して別途協議を行うこととする。
対応方針の詳細については、別紙に示す通りとする。
5.JC共闘は、共闘全体の交渉状況の掌握に努めると共に、2月28日(金)の「2003年闘争推進集会」を開催し、山場にむけた意思結集を行い、交渉の一層の追い上げを図っていく。
次回第4回戦術委員会は、「2003年闘争推進集会」を前にした2月28日(金)12時30分より開催する。
| <第3回戦術委員会確認事項 別紙> |
2003年2月20日
金属労協 |
| 賃金制度変更など会社主張に対する基本スタンス |
1.会社からの制度変更提案への対応
(1)賃金・処遇制度のあり方に関する金属労協の方針
金属労協は、97年に発表した「賃金・労働政策」において、今後の賃金・処遇制度の方向を示しています。それは、「ヒューマンな長期安定雇用」を基本としながら、生活保障の役割を担う年齢給と、技術・技能など労働の対価である職能給の2本立てを基本とし、必要生計費のミニマムを確保した上で、キャリア形成に応じた職務グループごとに異なる処遇となることも受け止めていくべきという複線型処遇制度の考え方に基づいたものです。また、雇用移動の増加等に対応して、仕事を基軸とした処遇の確立についても求めていくべきとしており、賃金・処遇制度の改定にあたっても、産業・企業実態を踏まえて、一定の幅を持ちつつ、是々非々で対応していくという考え方を持っています。
(2)賃金制度改定に関する労使協議の基本
しかし、賃金制度の改定は、通年的な労使協議の性格を持つものであり、制度内容はもとより、運用の透明性、結果に対する苦情処理など幅広い問題について、労使が慎重に話し合いを尽くした上で合意を図るべきものです。労働組合が現行制度に基づく賃金改定を交渉しようという時期に、交渉の基本となる制度改定を提案し、拙速な協議・合意を行おうとすることは、労使の信頼関係を損なうものと言わざるを得ません。賃金制度改定については、2003年闘争と切り離して、別途協議すべきです。
また、制度改定にあたっては、労使の話し合いによって、透明で納得性の高い賃金・処遇制度を構築することが重要です。制度設計・運用基準の明確化、評価制度の透明性と公正さの確保、日常のチェック機能のあり方、苦情処理機能などを含めて、十分な協議を行い、労使協定の締結を行う必要があります。
2.金属産業の生産性と国際競争力に対する考え方
(1)日本における金属産業の位置づけ
金属産業は、資本財や生産財をあらゆる分野の産業に供給しているという点でも、また輸出総額の8割(2002年)を占め、さらに金属産業における貿易黒字が全輸入額の9割を占めており、農産物や原燃料などの輸入をするための貿易黒字を稼ぎ出しているという点でも、まさにわが国の基幹産業であることは間違いありません。経済のソフト化・サービス化、あるいは第三次産業化が進む状況のなかにあっても、金属産業はそのようなサービス産業をも含めた日本経済全体を支える基幹産業であり、その重要性が失われるわけではありません。
(2)金属産業の生産性の実態
「経労委報告」では、「生産性に応じた人件費コストの決定が必要」と指摘していますが、OECDデータによれば、金属産業における単位労働コスト(雇用者1人あたり人件費÷就業者1人あたり付加価値)は、日本を100としてアメリカ111.5、ドイツ126.8、イギリス148.0などとなっており、生産性との対比で見た人件費の「割安さ」が際立っています。(「2003年闘争ミニ白書」P23)
(3)人的投資の重要性
中国の台頭をはじめとする国際競争の激化のなかで、わが国金属産業にとって、セル生産方式の導入や「ムダとり」の徹底など生産システムの抜本的な見直し、最先端分野、高機能・高品質製品の開発・生産を軸とした海外生産拠点との棲み分けが重要となっています。
これまで蓄積されてきた現場の技術・技能、情報や知恵を総動員することなしに、このような対応を進めることは不可能であり、現場における高度熟練の技術・技能の力をさらに強化していくことが不可欠です。
そのためには金属産業の生産性の高さにふさわしい適正な賃金水準、処遇が確立されなければなりません。2003年1月に発表された厚生労働省「ものづくり人材育成研究会報告書」は、「人材育成に対して積極的な投資を行うかどうかが、その企業の生き残りの分かれ目となる」と指摘しています。
(4)経営戦略の欠如
ここ数年の企業収益の動向を見てみると、例えば金属産業の98年度決算と2002年度決算予測(日銀・短観)を比べると、売上高営業利益率は1.1ポイント上昇していますが、売上高人件費比率は1.4ポイント低下しています。また、法人企業統計によれば、製造業の設備投資効率(付加価値額÷有形固定資産)は、98年度74.9%に対して、2001年度は69.4%へと大幅に低下しています。こうした状況は、まさに人件費の削減でしか利益を捻出できない、経営戦略の欠如を如実に表しているといえます。
一方で、2002年度決算において、史上最高益が予想されている企業もあり、同じデフレという条件下にあっても、経営戦略の違いによって、いわゆる「勝ち組」と「負け組」の差が際立つ状況となっています。業績悪化の原因を、すべてデフレや人件費コストのせいにすることは、経営者としての責任を放棄するものであり、容認することはできません。
(5)急がれる日本の高コスト是正
日本経団連「経労委報告」でも指摘されているとおり、金属産業をはじめとするものづくり産業の国際競争力にとって、日本における産業インフラコストの高さが重大な影響を与えています。2002年6月に経産省が発表した「平成13年度産業の中間投入に係る内外価格調査報告書」によると、日本の産業の中間投入コストは、全体としてアメリカの1.81倍、ドイツの1.58倍、中国の5.56倍となっています。
産業の中間投入において内外価格差が著しい分野は、参入規制と不適切な価格決定システムがとられてきた分野です。ものづくり産業の基盤強化の観点からも、国民生活向上の観点からも、こうした分野における参入・価格両面での規制の整理・撤廃によって、内外価格差是正が図られなければなりません。
|
<このページのトップへ>
<目次に戻る>
|